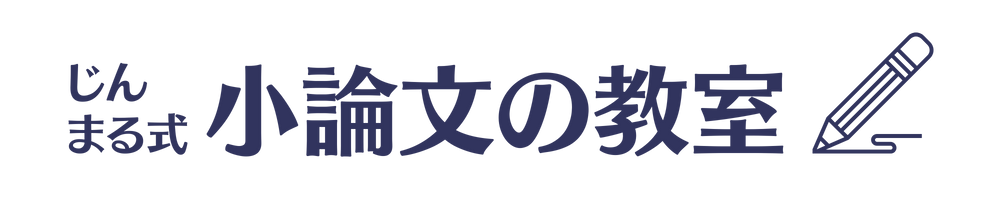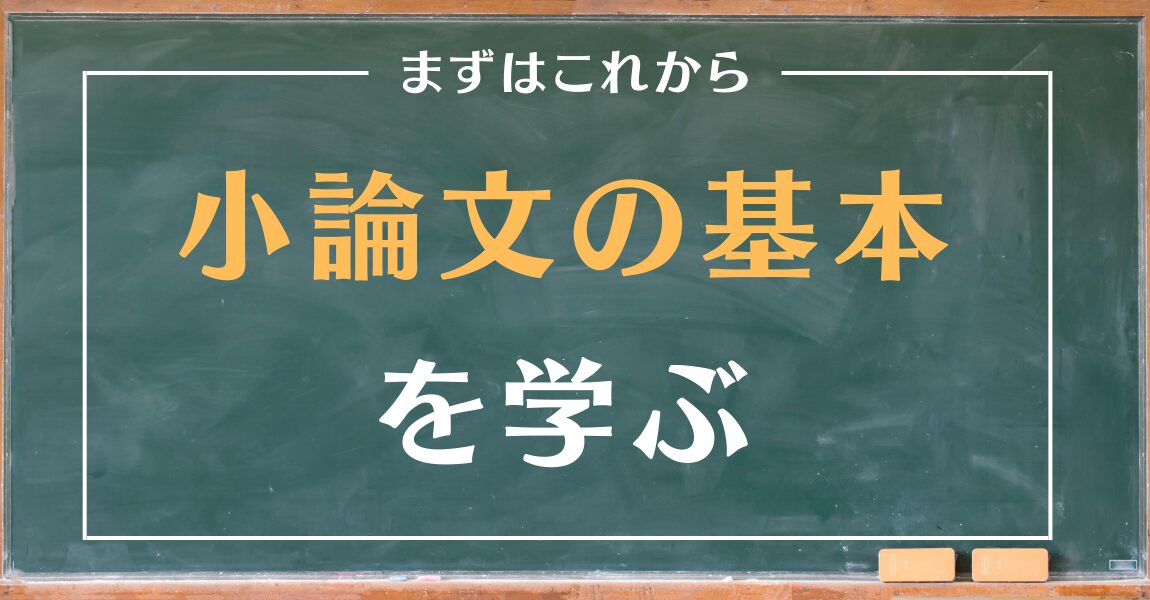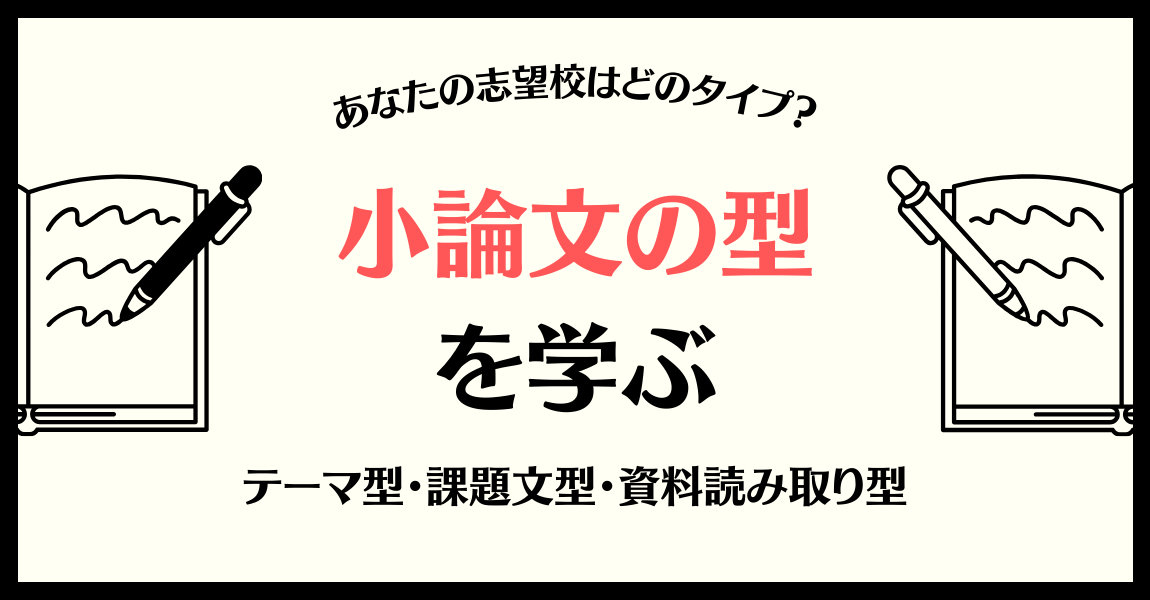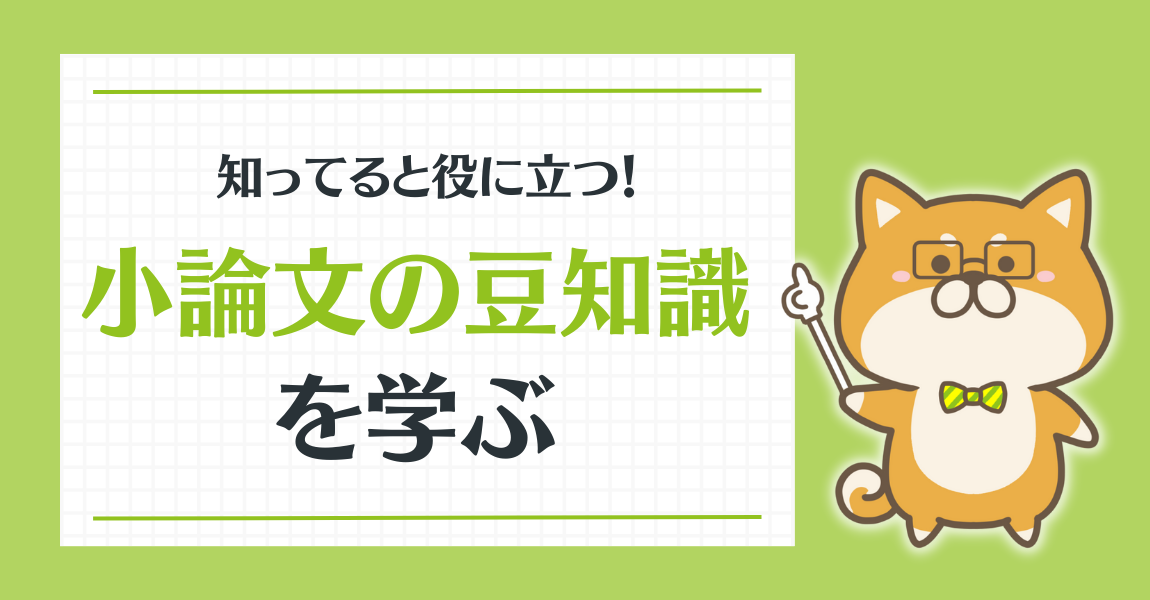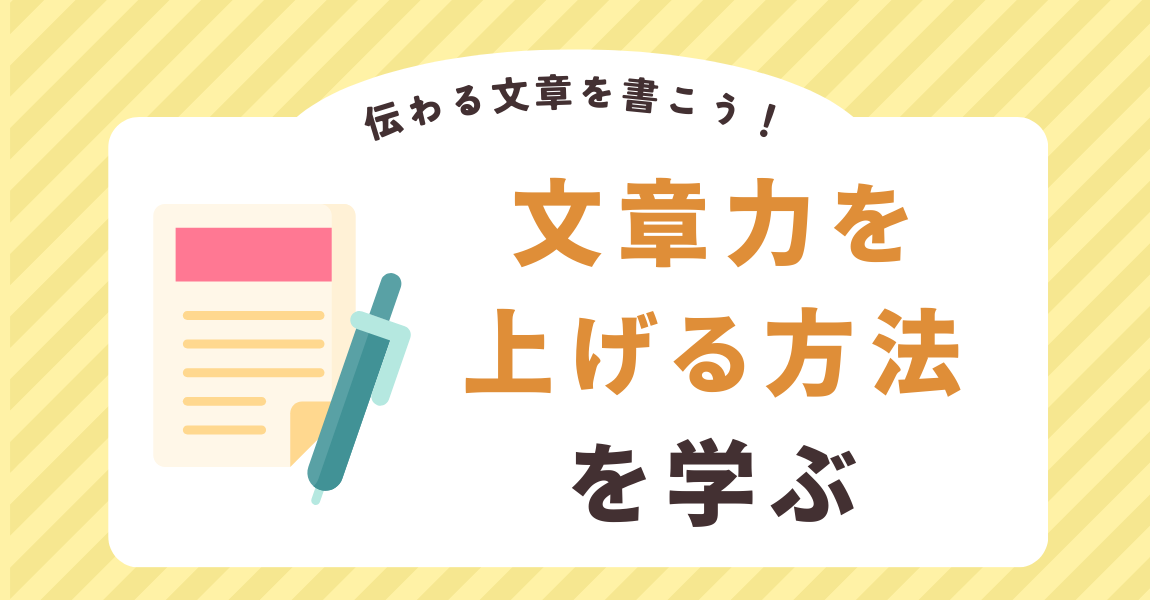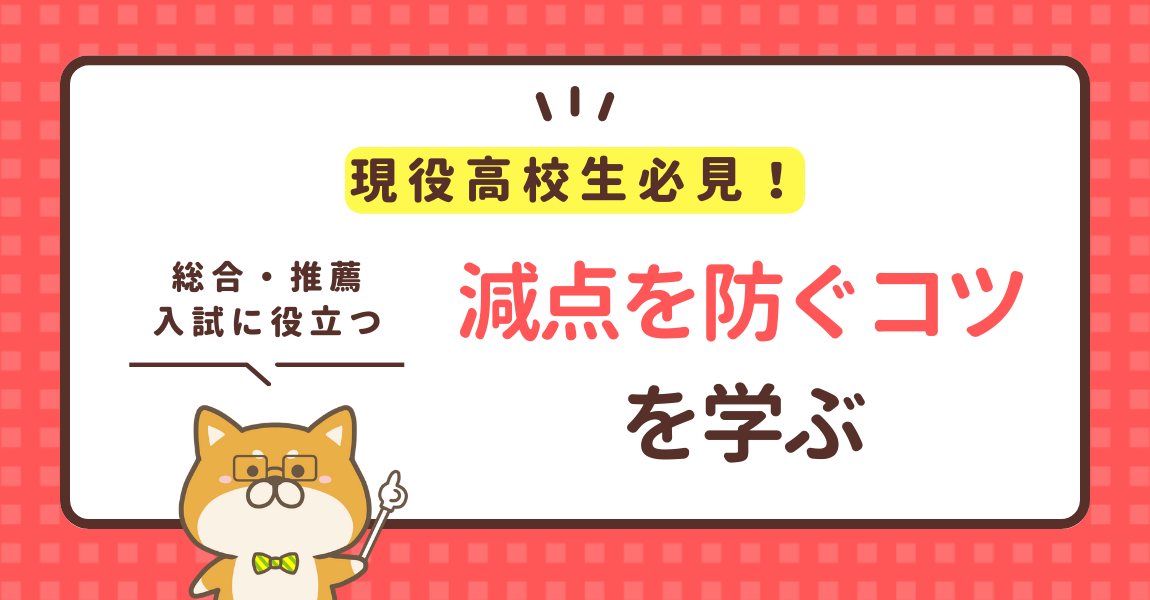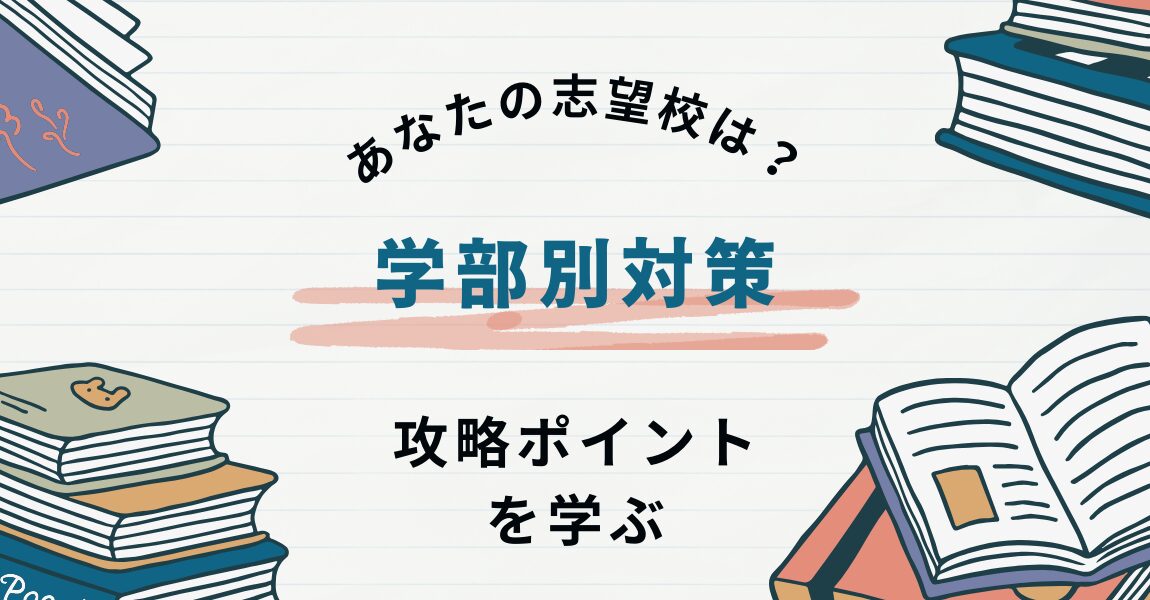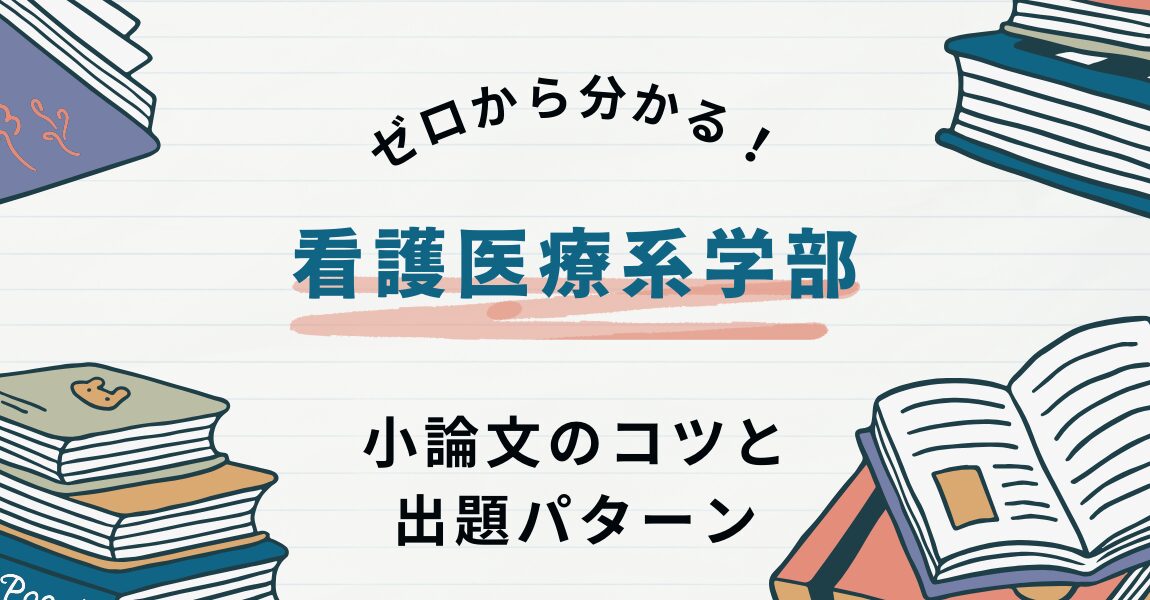【社会経済系学部】4つの頻出テーマを完全解説!(入試小論文対策)
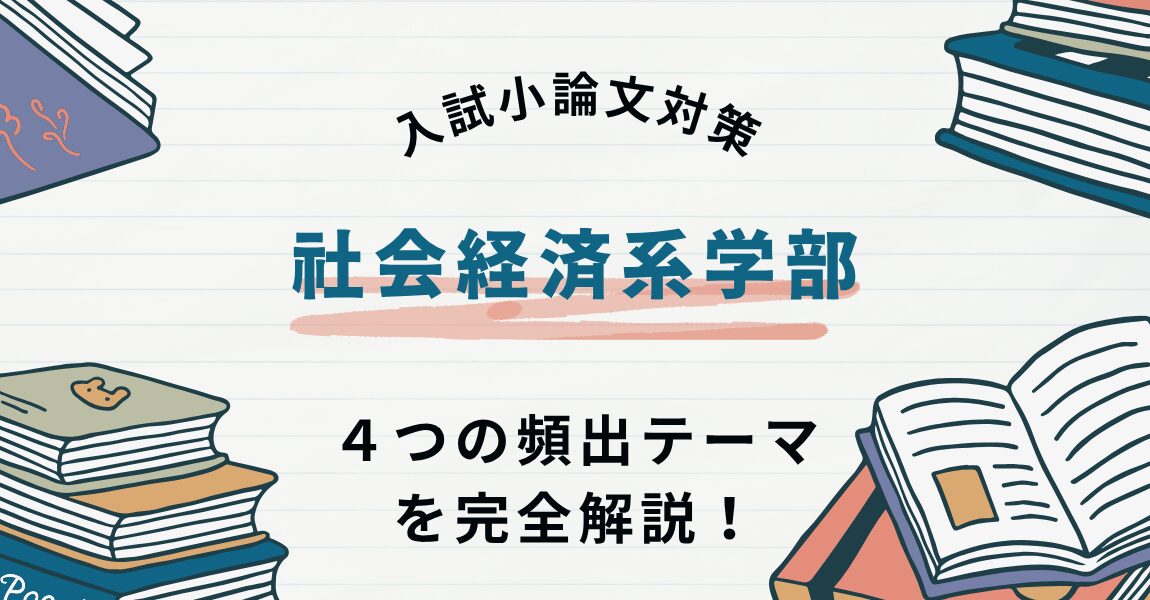
- 社会経済系の学部をめざす高校生
- 小論文で使える知識を身に付けたい人
- 総合型選抜や学校推薦型選抜で合格点を取りたい人
この記事では、「社会経済系学部の頻出テーマ」を取り上げて、なるべく分かりやすく説明します。
小論文でより高い点数を取りたい高校生は、この記事で一緒に勉強していきましょう。
社会経済系学部の小論文を攻略しよう

社会経済系の学部ではどんなテーマが出題されるんですか?

テーマが幅広くて、何から手を付けたらいいか分かりません。

この記事を読んで「社会経済系学部の頻出テーマ」を勉強すれば、合格レベルの小論文を書けるようになりますよ。
よく出題される4つのテーマと考え方
小論文は、ただ知識を並べるだけでは点数になりません。どんなテーマが出ても、「なぜそれが問題なのか」「どうすれば解決できるのか」を整理する力が大切です。
そして、あらゆるテーマに対応するには、浅く広くでもいいので社会の話題に触れておく必要があります。試験直前に詰め込むよりも、少しずつ考える習慣をつけておく方が効果的です。
この記事では、社会経済系でよく出る4つのテーマを取り上げます。それぞれの背景と、書くときの考え方を見ていきましょう。
① 社会保障と支え合い ―「助け合う仕組み」をどう続けるか
テーマの背景と狙い
社会保障のテーマでは、公的年金や医療制度、ベーシックインカム(すべての人に一定の金額を支給する制度)など、「人を支える仕組み」をどう維持するかが問われます。
現在の日本では、少子高齢化が進み、働く世代が減る一方で、支えられる側は増えています。
「このままの制度で続けられるのか」という不安が高まるなか、国と個人の負担の分け方が大きな課題になっているのです。
国がどこまで支え、個人がどこまで担うのか。お金の流れ(負担と給付)をどう整えれば公平で安心できる社会になるのか。
このように、「社会の中でどう助け合うか」を考えることが、このテーマの重要なポイントです。
書くときの考え方
- 制度の目的を明確にする
社会保障は「弱い立場の人を守る」だけでなく、「社会全体の安定を保つ」仕組みでもあります。なぜ必要なのかをはっきり示すことで、話の軸がぶれません。 - 課題を整理する
現役世代の負担増や財源不足、世代間の不公平などを具体的に整理します。身近な例やデータを入れると、説得力が増します。 - 現実的な改善策を提案する
「高齢者の就労支援」「税金による補助」「若者の負担軽減」など、実行可能な案を考えます。理想論で終わらせず、現実的な視点を持つことが大切です。
② 労働とグローバル化 ―「人の動き」が社会を変える
テーマの背景と狙い
このテーマでは、外国人労働者の受け入れ、働き方改革、雇用の多様化などが扱われます。
日本では少子化によって働き手が減り、海外からの人材に頼る動きが広がっています。
しかし、人手を増やすだけでは解決できません。文化や言葉の違いをどう受け入れるかが、これからの大きな課題です。
また、テレワークや副業など、働き方そのものも変化しています。コロナ禍以降、在宅勤務が一般化し、企業に属しながら個人で仕事を受ける人も増えました。
AIやデジタル技術の進歩により、働く自由が広がる一方で、成果の評価やワークライフバランスといった新しい問題も出てきています。
経済の発展と働く人の幸福をどう両立させるか。制度や仕組みの変化を並べるだけでなく、働く人の視点をどう盛り込めるかが大切です。
書くときの考え方
- 人を中心に考える
企業の利益ではなく、働く人の生活や安心を軸に考えましょう。経済成長と個人の幸福をどう結びつけるかがカギになります。 - 多様性と共生を意識する
外国人労働者が安心して働けるよう、教育支援や地域の理解を広げる工夫を提案します。言葉や文化の違いを前提に考えることがポイントです。 - 新しい働き方をどう支えるか
AIの導入やリモートワーク、副業などを前向きにとらえ、柔軟な働き方を支える制度を考えてみましょう。
③ 観光と地域経済 ―「地域の豊かさ」を守るために
テーマの背景と狙い
観光は地域を元気にする重要な産業ですが、観光客の増加が環境や住民の生活に影響を与えることもあります。
特に京都や沖縄では、オーバーツーリズム(観光客の集中による問題)が深刻化しています。交通渋滞や騒音、ゴミ問題などを耳にすることも多いのではないでしょうか。
このテーマの狙いは、「地域の発展」と「住民の暮らし」をどう両立させるかを考えること。経済の利益を追うだけでなく、自然や文化を守る視点も必要です。
観光による利益を地域全体で分かち合いながら、持続可能な仕組みを築けるかが問われます。
書くときの考え方
- 関係者の立場を整理する
行政、住民、観光客、企業など、関わる人の立場を整理しましょう。誰が得をして、誰が困っているのかを明確にすることで、問題の全体像が見えてきます。 - 持続可能な観光を提案する
観光地の分散化、公共交通の整備、マナー教育など、経済と環境を両立させる具体的な提案を書いてみましょう。 - 地域文化を守る意識をもつ
観光は文化を「見せる」と同時に「守る」行為でもあります。伝統や祭り、地域の暮らしをどう未来へつなぐかを考えてみましょう。
④ 制度と未来 ―「どんな社会を設計するか」
テーマの背景と狙い
AIやデジタル技術の進歩によって、私たちの生活や社会の仕組みは大きく変わっています。
買い物や医療、行政手続きなどが便利になる一方で、これまでの制度が時代に合わなくなり、新しい課題も生まれています。
たとえば、AIによる自動化で仕事の一部がなくなるかもしれません。リモートワークが広がって働き方は自由になりましたが、税金や社会保険の制度が追いついていないという問題もあります。
このような変化の中で、社会のルールや仕組みをどう作り直すかが問われています。このテーマでは、技術そのものよりも、それをどう活かしていくかが大切です。
公平さ、効率、自由、持続可能性など、どの価値を重視するかによって、社会の形は変わります。「変化を恐れるのではなく、どう生かすか」「人がよりよく生きるためにどんな制度が必要か」を考えてみましょう。
書くときの考え方
- 変化の両面を捉える
技術の進歩には、便利さとリスクが共存します。効率だけでなく、公正さや人間らしさをどう守るかを考えましょう。 - 公平な制度を考える
税制、教育、雇用など、社会を支える仕組みをどう整えるか。公平さと柔軟さを両立させる視点がポイントです。 - 現実に基づいた提案をする
理想論だけでなく、実際の課題(少子化、格差、技術の不均衡など)を踏まえた制度の形を提案してみましょう。
実際に小論文を書いてみよう
社会経済系の小論文でよく出るテーマの全体像がつかめたら、次は実際に書いてみましょう。
先ほど説明した4つのテーマの中から、具体的な練習問題を用意しました。ぜひ挑戦してみてください。
日本の公的年金制度について、あなたの意見を800字以内で述べよ。
インバウンドの増加に伴う問題をひとつ取り上げ、あなたの考えを800字以内で述べよ。
ベーシックインカムの導入について賛成か反対か、あなたの考えを800字以内で述べなさい。
少子高齢化による労働力不足を背景とした外国人労働者の受け入れについて、日本が直面する課題と、それに対する解決策を800字以内で論じなさい。

調べながらでもいいので、書いてみることが合格への近道です!
これらの問題の模範解答とポイント解説を、公式noteで公開しています。
気になる方は、以下のリンクからぜひチェックしてください。
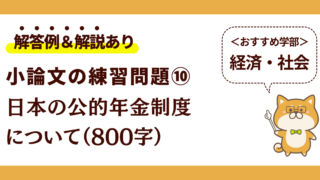
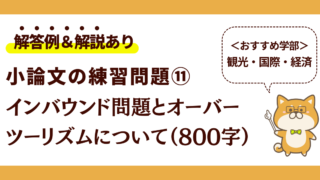
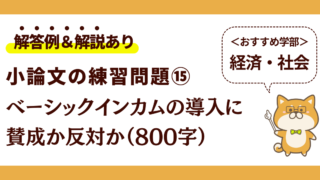
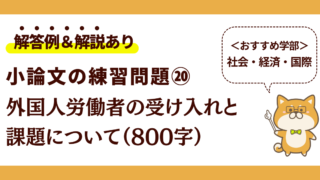
社会経済系学部の頻出テーマまとめ
「社会経済系学部の頻出テーマ」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
小論文は、正解を探す試験ではなく、自分の考えをつくる試験です。
社会で起きていることを、自分の言葉で説明できるようになると、どんなテーマにも対応できるようになります。
社会問題は、ニュースや授業の中だけでなく、私たちの身の回りにもあります。身近な出来事を「なぜ」「どうすれば」と考えることが、入試で問われる思考力を伸ばす第一歩です。
焦らず一歩ずつ、自分の視点で社会を見つめる力を磨いていきましょう。その積み重ねが、入試本番で「自分の言葉で書ける答案」を作る力になります。
- 社会保障と支え合いについて:社会の中でどう助け合うか?
- 労働とグローバル化について:「経済の発展」と「働く人の幸福」の両立
- 観光と地域経済について:「地域の発展」と「住民の暮らし」の両立
- 制度と未来について:社会のルールや仕組みをどう作り直すか?
小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。
この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。
何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!
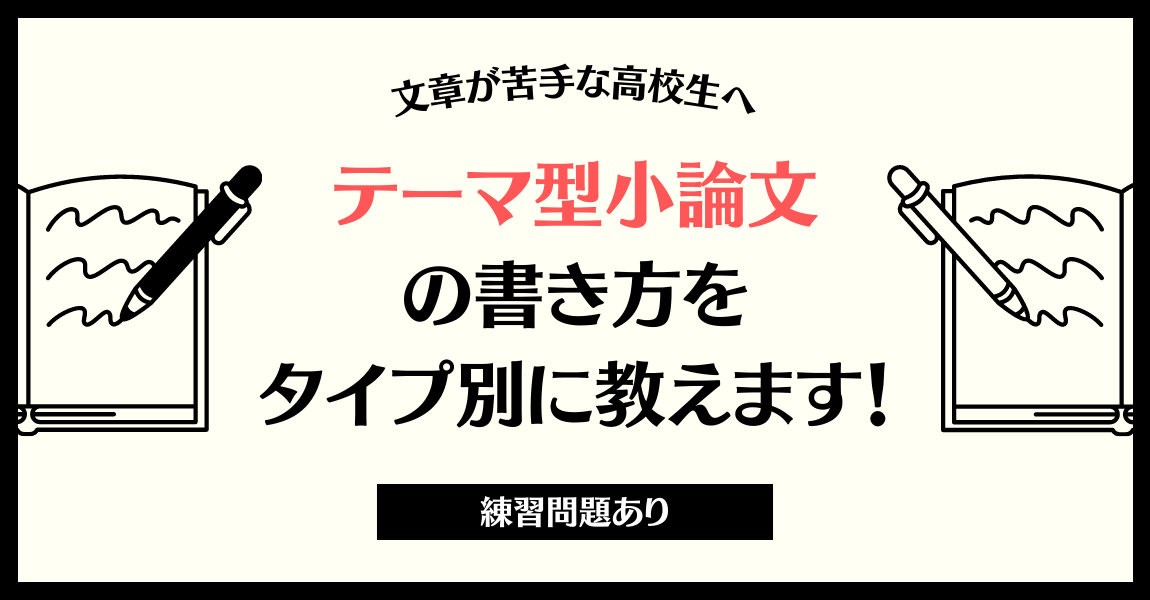
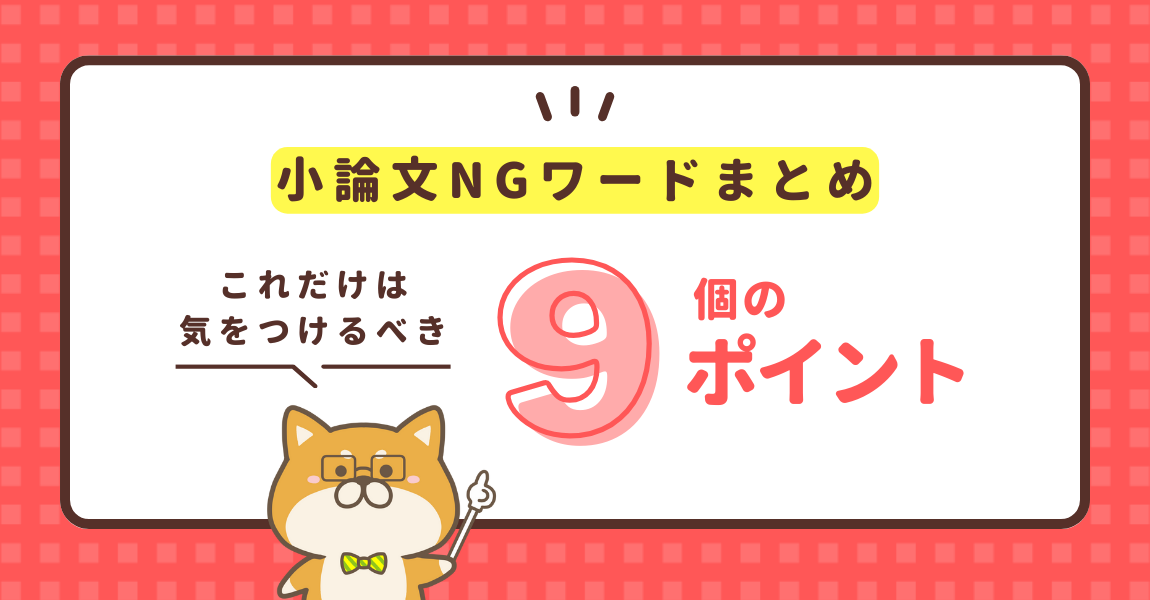
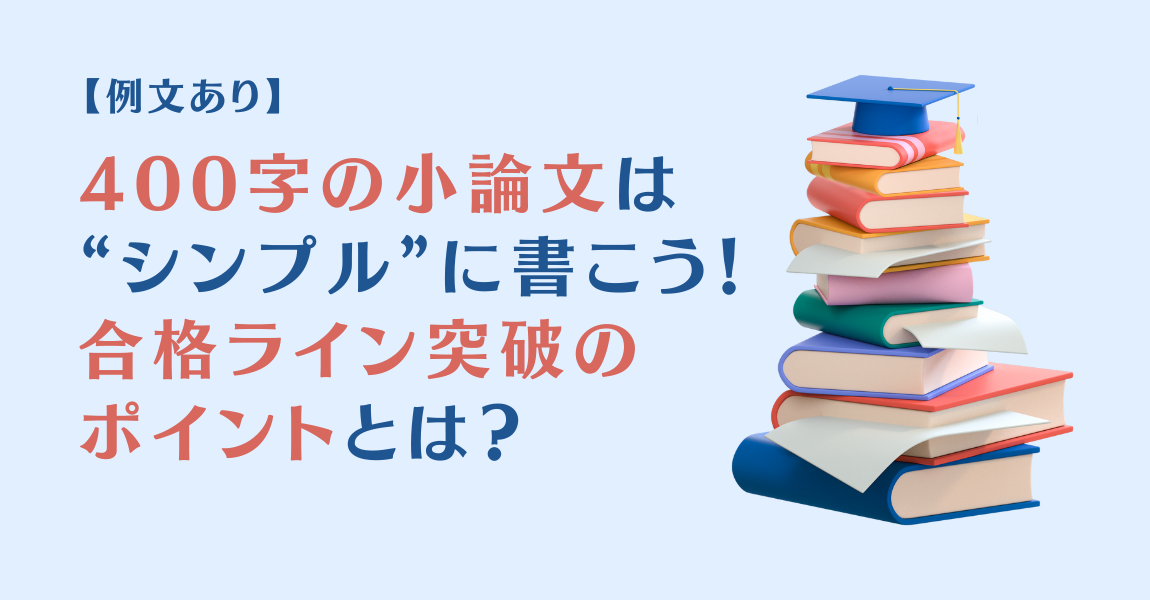
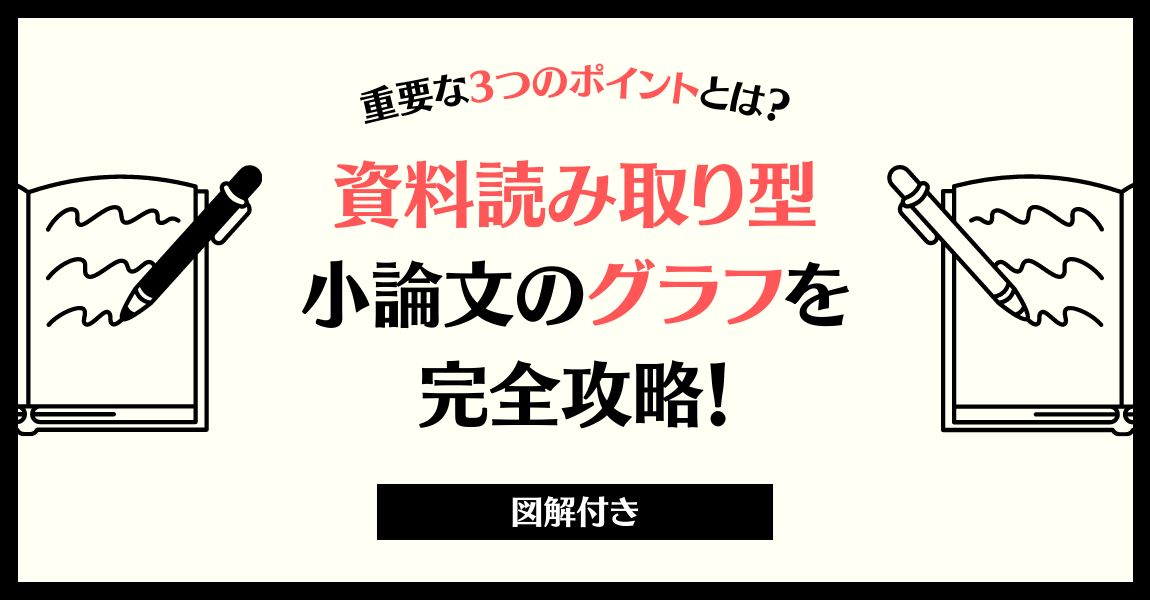
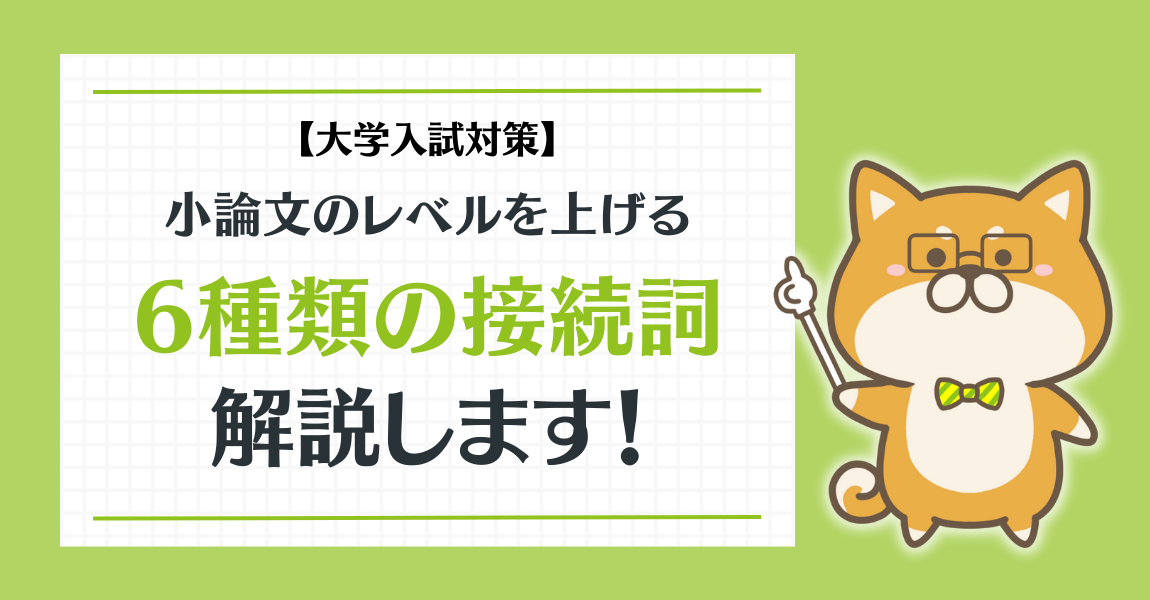
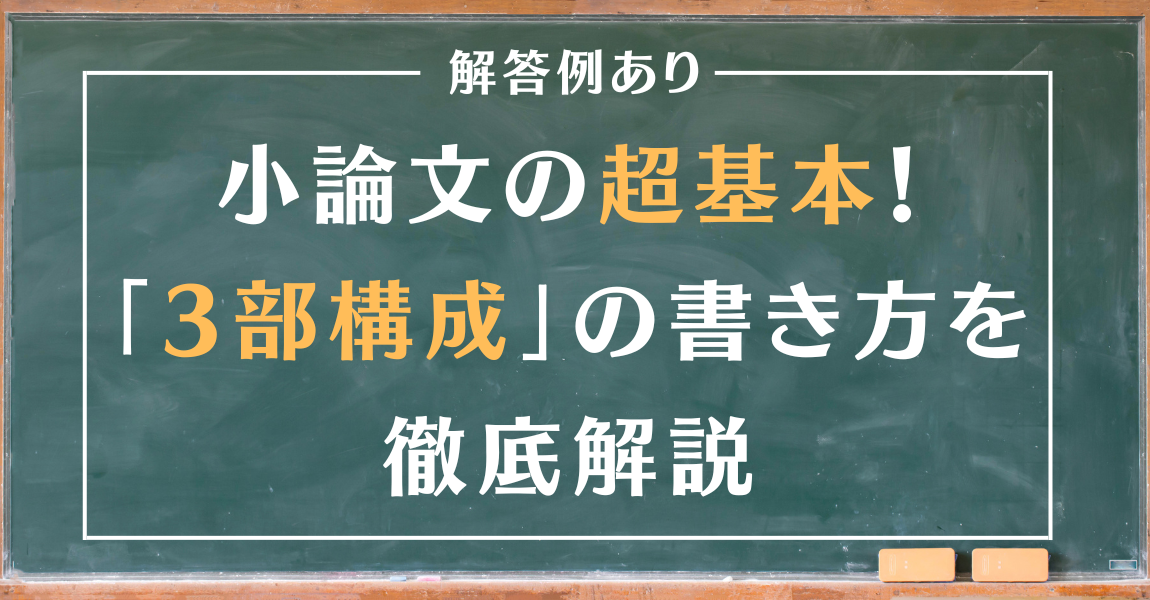

\役に立ったらシェアしてください!/