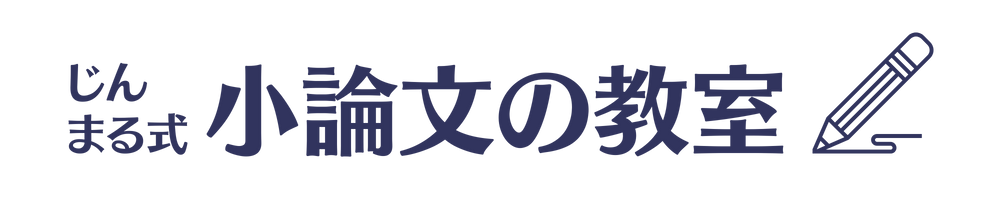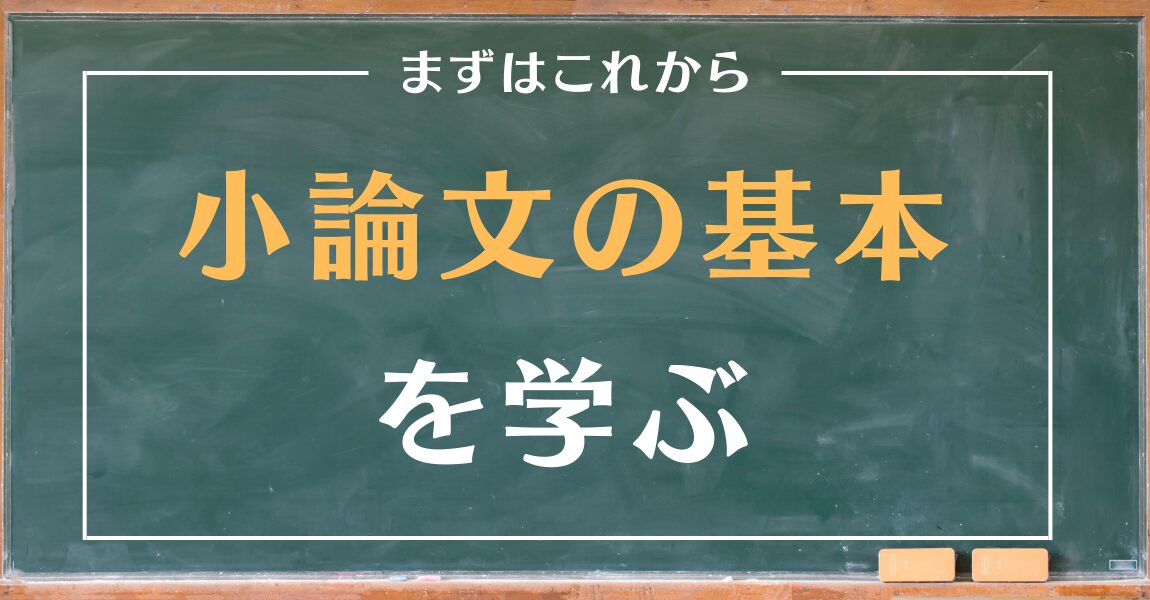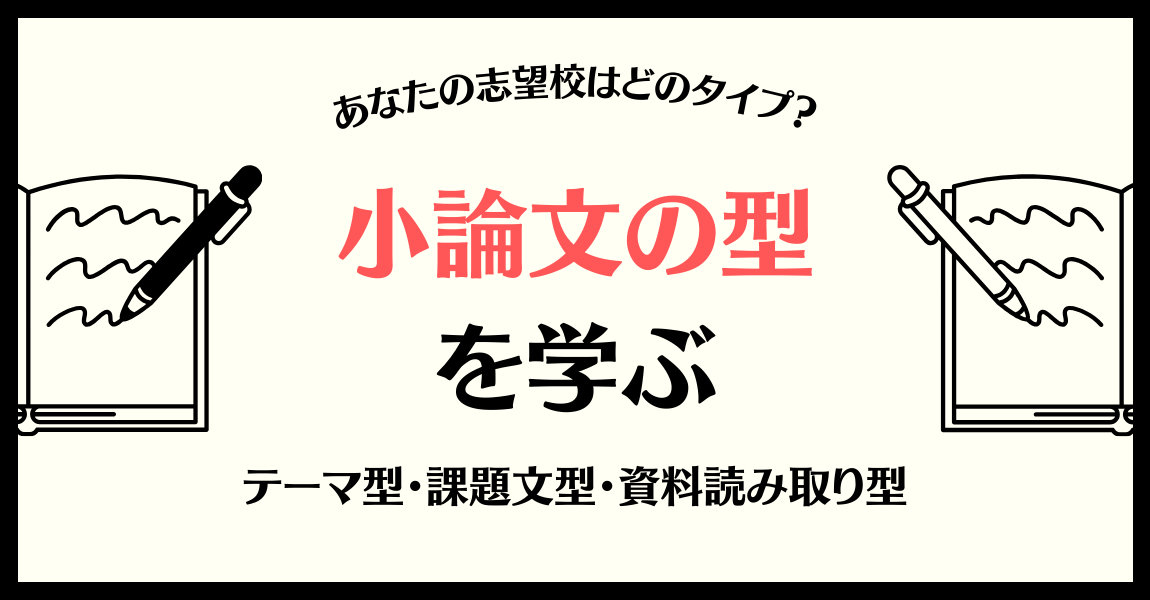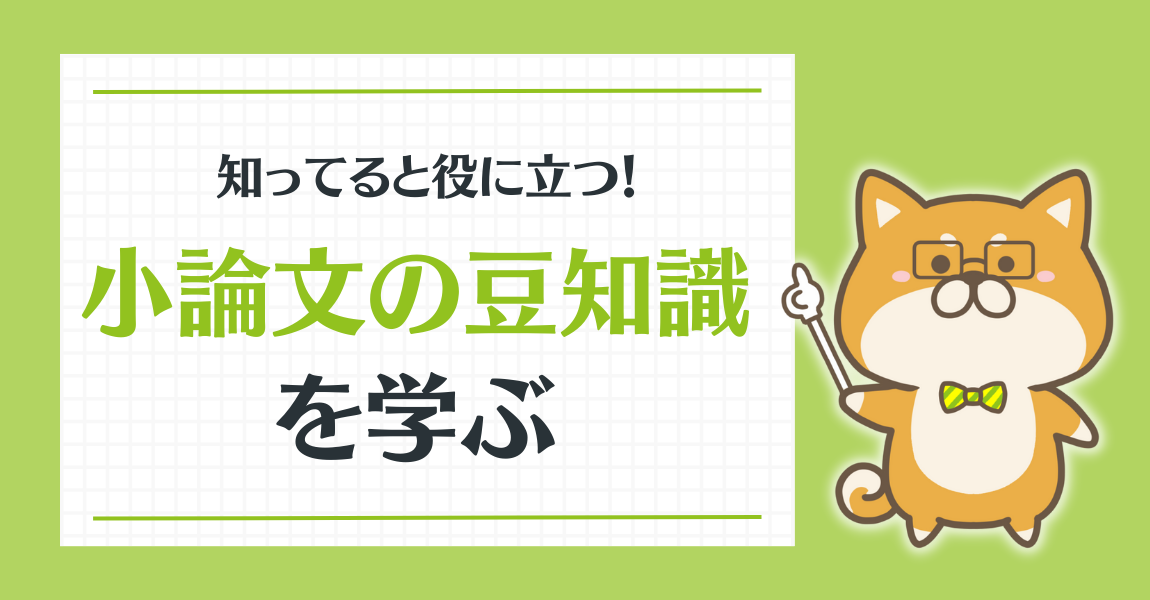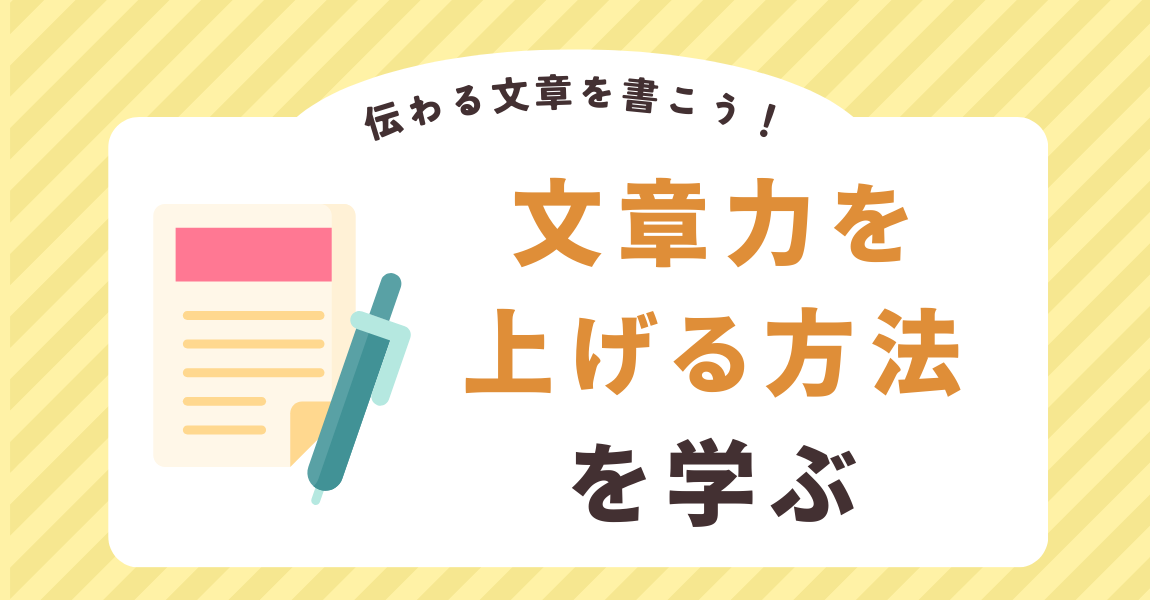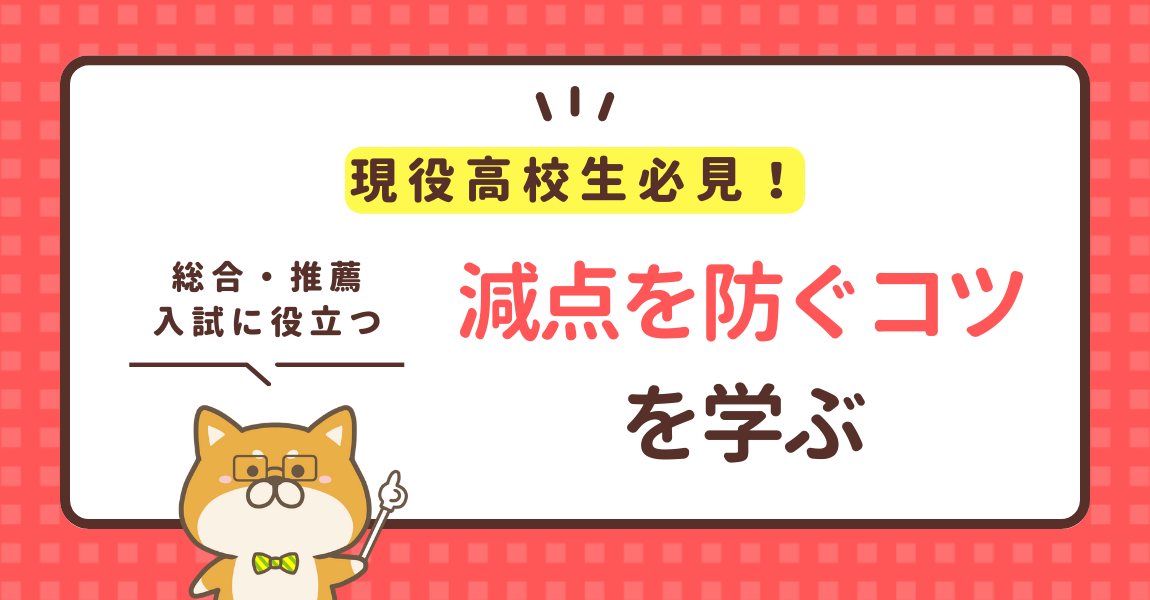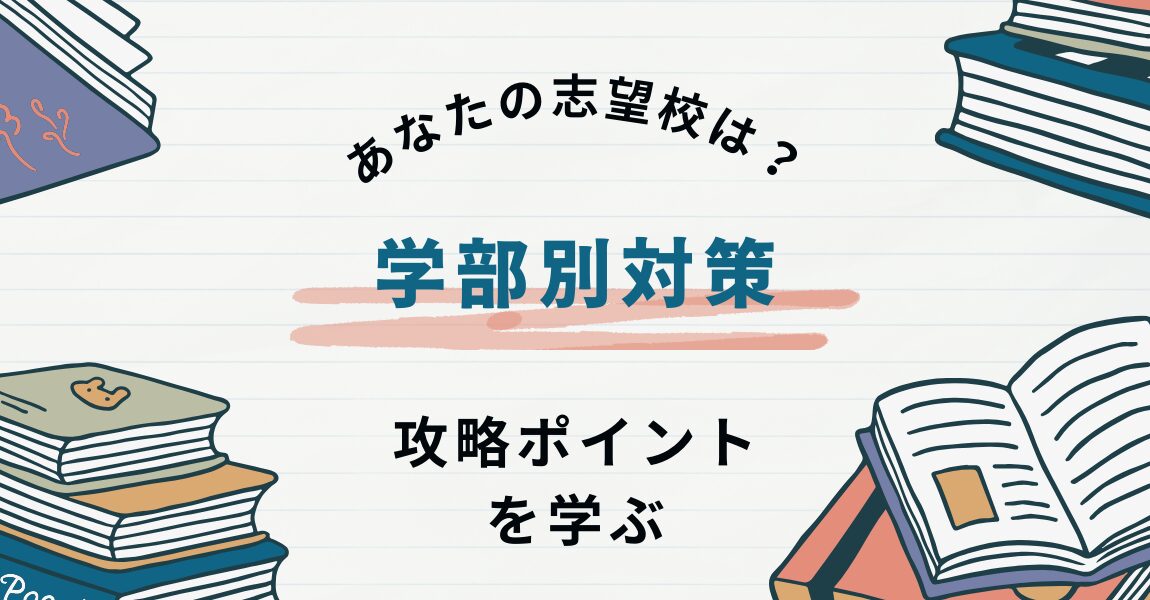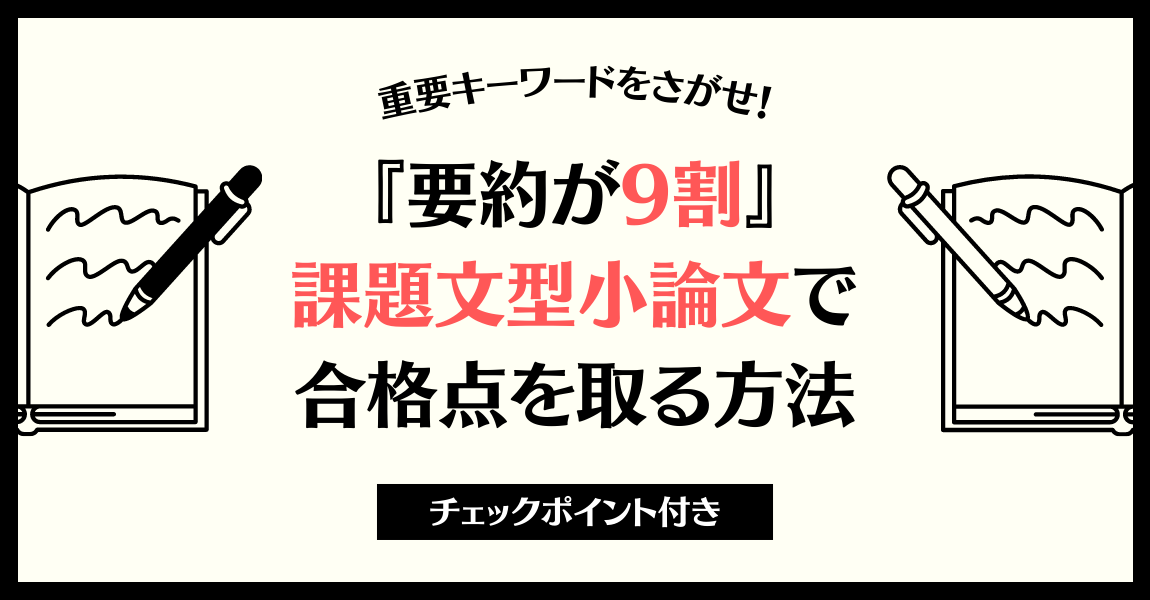【文章が苦手な高校生へ】テーマ型小論文の書き方をタイプ別に教えます!(練習問題あり)
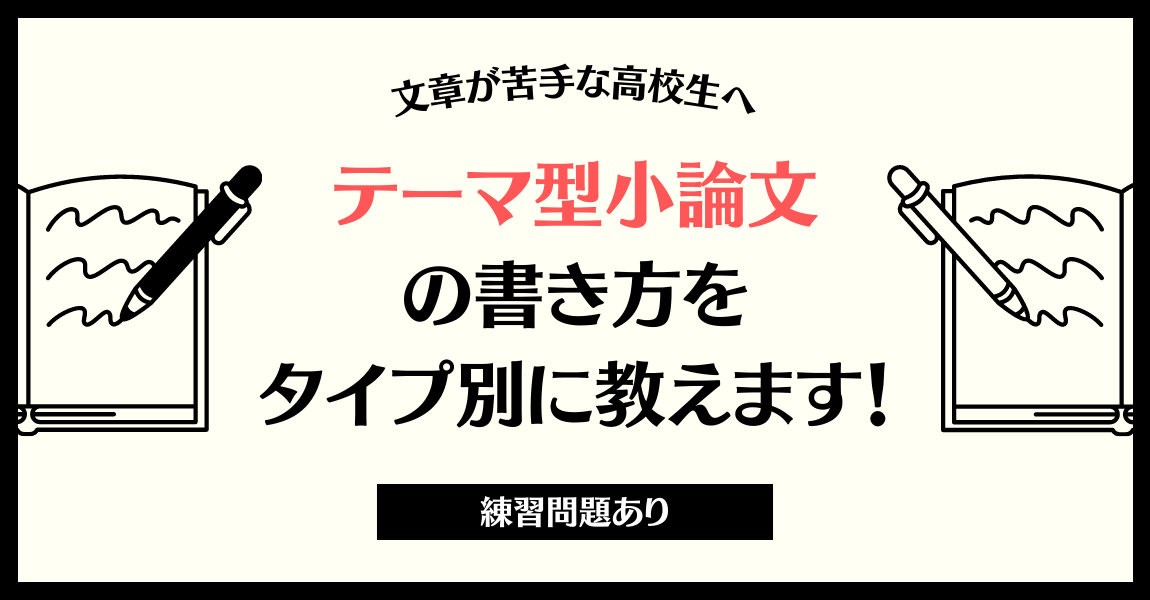
- 志望校の小論文がテーマ型
- 何から手を付けたらいいか分からない
- 手っ取り早く書けるようになりたい
この記事では、「テーマ型小論文の書き方」についてなるべく分かりやすく説明します。
テーマ型小論文の特徴を理解して、志望校対策を有利に進めましょう。
テーマ型小論文の書き方を学ぼう!

志望校の問題がテーマ型っぽいんですが、全然書けなくて・・・

何から対策を始めたらいいんですか?

この記事で「テーマ型小論文の書き方」を理解すれば、書き方が分かるようになりますよ。
小論文には決まった型がある
今このブログを読んでいるあなたも、すでに小論文対策を始めていると思います。
しかし、何から手を付けたら良いのか分からなくなった経験はありませんか?
安心してください。それは受験生の誰もが通る道です。
なぜなら、小論文は何の知識もナシに突然書けるようなものではないから。
そして、小論文の中には種類(型)があり、それぞれ書き方が大きく異なるんです。
残念ながら、それを知らずにいくら練習しても、小論文が書けるようにはなりません。
合格する小論文を書くには、それぞれのポイントを押さえておく必要があるんです。
問題のテーマを正確に読み取ろう
この記事で勉強するテーマ型小論文は、文字通り「テーマに沿って書く」ことが求められます。
そのため、設問のテーマは何なのか、何を求められているのかを正確に把握しなくてはいけません。
そのうえで自分の考えを掘り下げ、結論を導き出していく必要があるんです。

じんまる先生、さすがにそれは分かってますよ。

自分でも気付かないうちに、結論がテーマからズレてしまう高校生が多いので要注意ですよ。
どれだけ良い文章が書けていたとしても、テーマとかけ離れていては点数に繋がりません。
そして最悪の場合は、合格点に届かないということも考えられます。
せっかく努力した時間をムダにしたくないですよね?
そうならないためにも、テーマ型のポイントを理解して、減点されない小論文をマスターしましょう。
テーマ型小論文は全部で3タイプ
それではさっそく書き方の説明を、、、と言いたいところですが、その前にお伝えしておかなくてはいけないことがあります。
実は、テーマ型小論文だけでも大きく3タイプに分かれているんです。

それぞれのタイプを簡単に説明すると、以下のようになります。
ここからは、例題を参考にして実際に書き進めるための手順をお伝えしていきます。
志望校の小論文で出題されるタイプがすでに分かっている方は、当てはまる部分だけ読んでいただいても構いません。
1)意見対立型

以下のような問題が「意見対立型の小論文」です。
小学生がスマートフォンを利用することについて賛成か反対か、あなたの意見を述べなさい。
意見対立型の小論文では、設問のなかで2つの選択肢が与えられます。
例題1で言うと「賛成か反対か」にあたる部分です。
2つの選択肢からあなたが共感できる方を選び、その理由を考えながら書いていきます。

賛成と反対どちらを選んだ方が有利なんですか?

どちらが有利ということはありません。選んだ根拠を明確にするのが重要なので、自分が書きやすい方を選ぶようにしましょう。
意見対立型の小論文を書くときは、以下の手順で取り組んでみてください。
①根拠を書き出す
②自分の立場を決める
③準備した内容をもとに書く
①根拠を書き出す
意見対立型の小論文では、文章を書き始める前にやっておくべきことが2つあります。
まずひとつめは、小論文の軸となる根拠を考えることです。

なぜ賛成なのか?(どうして反対なのか?)ということですね。
そして意見対立型の小論文の場合、それぞれの立場から見たメリットやデメリットが根拠となります。
まずはそれらを書き出すこと(メモ作り)から始めましょう。
この作業は、とにかく量が勝負です。
また、きれいに書く必要はありません。
自分さえ分かっていれば、箇条書きでも殴り書きでも、どんなかたちでもOK。
実際に使えそうな意見ではなくても、どんどん書き出していきましょう。
メモの作り方については、以下の記事で詳しく解説しています。
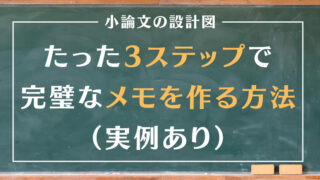
②自分の立場を決める
2つめは、メモした根拠をもとに自分の立場を明確にすることです。
まず、①で書き出したメモの中から、これが書きやすそうだなというものを選びます。
そして選んだ内容をもとに、自分が主張する立場を決めていきましょう。
意見対立型の小論文では、とにかく自分の立場を明確にすることが重要です。
そのため、この作業が小論文のできばえを左右するといっても過言ではありません。

適当に書き始めるのではなく、自分がその選択肢を選んだ理由を明確にしてから取り組むようにしましょう。
ちなみに、賛成の場合はメリット、反対の場合はデメリットで挙げた内容が、自分の意見に対する根拠となります。
選ぶ個数の目安としては、400字の場合は1つ、600字~800字の場合は2つ、1000字以上の場合は3つ程度がいいでしょう。
③準備した内容をもとに書く
ここまできたら準備OKです。
いよいよ小論文を書き進めていきます。
ここで改めて、小論文の基本となる「3部構成」を確認しておきましょう。
・序論では「自分はどちらの立場か」を明確にする
・本論では「選んだ根拠」をもとに自分の意見を述べる
・結論では「自分の主張」を一言でまとめる
小論文の書き方を忘れてしまったという方は、以下の記事を参考にしてください。
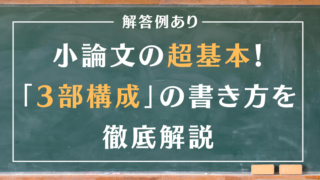
2)問題解決型

以下のような問題が「問題解決型の小論文」です。
日本における少子高齢化問題の解決策について、あなたの考えを述べなさい。
問題解決型の小論文では、出題テーマに関連する問題点をひとつ取り上げます。
そして、原因や解決策を考えて文章にまとめていきましょう。
ただし、意見対立型の小論文のように選択肢が提示されているわけではありません。
そのため、何を軸にして書くのかを明確にしておく必要があります。
言い換えると、そこさえきちんと押さえておけば、難なく書き進めることができます。
それでは早速、以下の手順で取り組んでみましょう。
①問題点を書き出す
②原因と解決策を考える
③準備した内容をもとに書く
①問題点を書き出す
まずは、出題テーマの問題点を考えてみましょう。
このときに大切なのは、いろいろな角度から考えてみることです。

例題2の場合、少子高齢化といっても経済的不安や保育士不足など、さまざまな問題が挙げられますよね。
少子高齢化をひとつの問題として捉えてしまうと、何から手を付けたらいいのか分からなくなってしまいます。
そのため、まずは大きな問題を分解して考えることが重要です。
練習のうちは最低でも3つ書き出してみてください。
②原因と解決策を考える
問題点を書き出したら、その原因をひとつずつ考えてみましょう。
思い浮かんだ問題点に対して「なんで?」「どうして?」という視点からどんどん掘り下げます。
この作業を2~3回繰り返し、小論文の軸にする問題点を絞り込んでいきましょう。
問題の原因がはっきりしたら、次に解決策を考えます。
ここで気をつけて欲しいのは、その解決策は実現可能か(非現実的ではないか)ということです。
あまりにも現実離れした意見では、説得力にかけてしまいます。
目新しいアイデアを書く必要はありませんので、実現できそうな解決策を書くようにしてください。
③これまでの内容をもとに書く
問題点、原因、解決策の3つが揃ったら、あとは型にはめて書くだけです。

「問題点を明確にする→原因を述べる→解決策と自分の意見をまとめる」という順番で進めましょう。
この順番が前後してしまうと、意味の通じない文章になってしまいます。
書いているうちに分からなくならないように、メモを作る順番にも気を付けましょう。
また、問題解決型の小論文は“Yes”または“No”では答えることができません。
そのため自分自身で問題点を考え、解決策を提示する必要があります。
ここが曖昧なまま書き始めてしまうと、文章がねじれてしまう原因になります。
最後まで一貫した文章を書くにも、序論の段階で解決策を明記するように心掛けてください。
小論文の書き方を忘れてしまったという方は、以下の記事を参考にしてください。
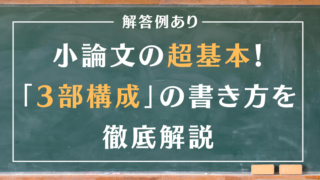
3)意見提示型

以下のような問題が「意見提示型の小論文」です。
義務教育におけるオンライン授業の導入について、あなたの意見を述べなさい。
意見提示型の小論文では、出題テーマに対する自分の意見を書いていきます。
何を書けばいいのか分からないという人がいるかもしれませんが、難しく考えなくて大丈夫。
ここで例題3に注目してみましょう。
あるものが隠されているのですが、何だか分かりますか?
実はこの問題、「義務教育におけるオンライン授業の導入について(賛成か反対か)あなたの意見を述べなさい。」となっているのです。

このパターンに見覚えはありませんか?
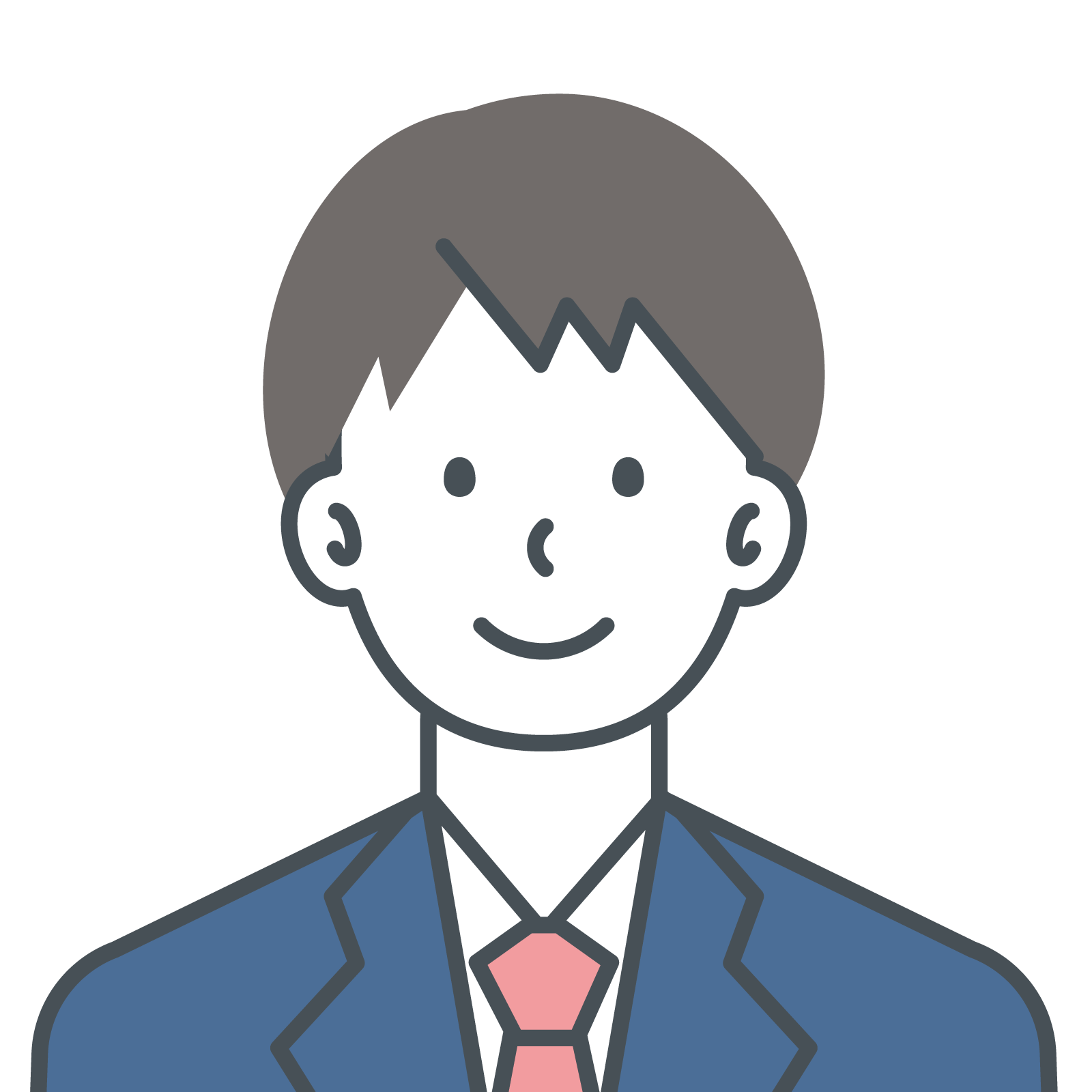
あ!意見対立型の小論文と同じです!

そのとおり!意見対立型の小論文と同じように書き進めれば問題ありません。
小論文の書き方を忘れてしまったという方は、以下の記事を参考にしてください。
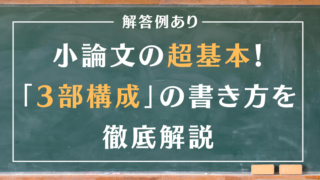
テーマ型小論文まとめ
この記事では「テーマ型小論文の書き方」について解説しました。
このタイプの小論文は、課題文や資料がないため解答の自由度が高いです。
しかしその反面、知識量によって書く内容に差が出やすいという特徴もあります。
日ごろから志望学部や学科に関連したニュースを見たり、関連書籍を読んだりしながら、専門知識を深めておきましょう。

このような積み重ねが、受験本番の点数に大きく影響しますよ。
小論文のネタ集めに困っている人は、高校生向けの新聞がおすすめです。
普段新聞を読まない高校生でも分かるように、時事問題や重要なキーワードがまとめられています。
効率よく学ぶことができるので、忙しい高校生にぴったりの学習方法なんです。
以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
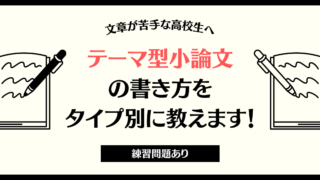
1)意見対立型:共感できる選択肢を選び、その理由を提示する。
2)問題解決型:問題点をひとつ取り上げ、原因や解決策を提示する。
3)意見提示型:共感できる選択肢を選び、その理由を提示する。
小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。
この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。
何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!
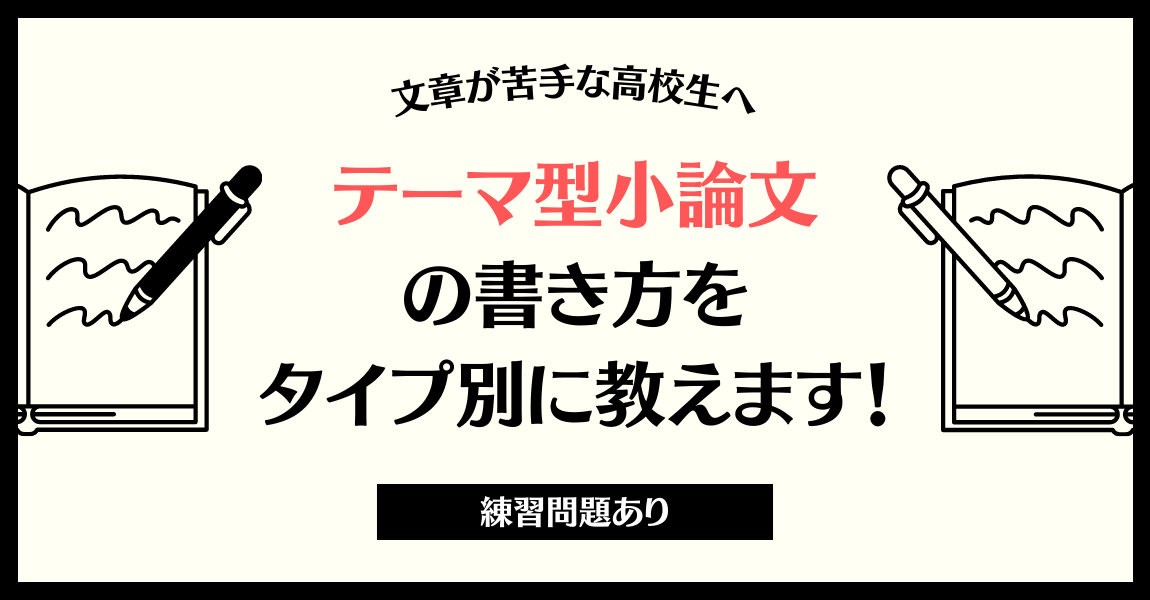
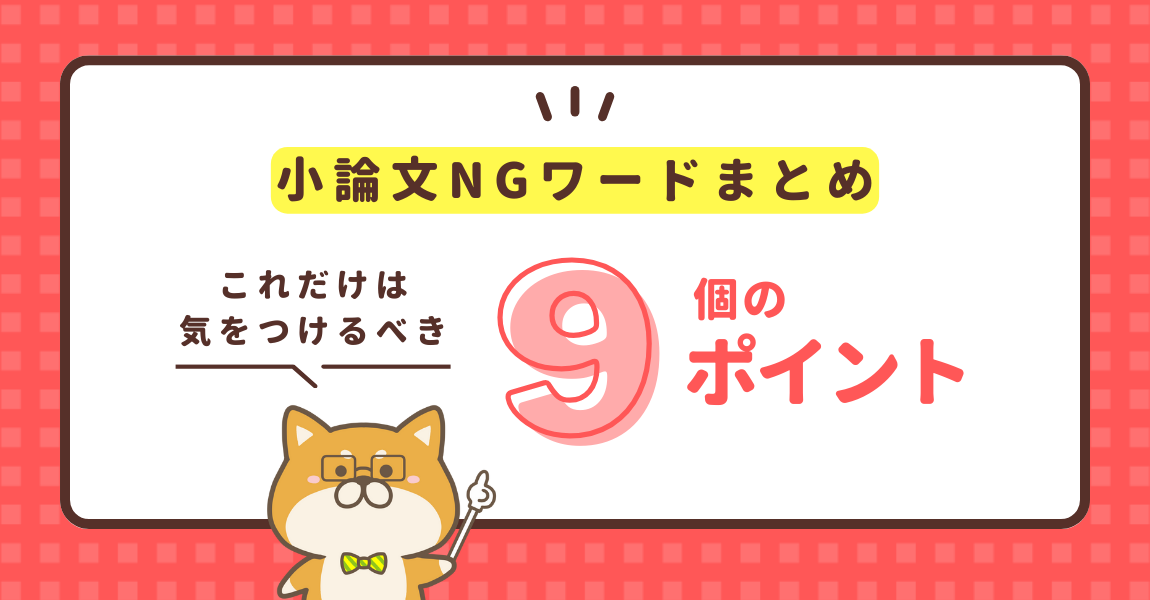
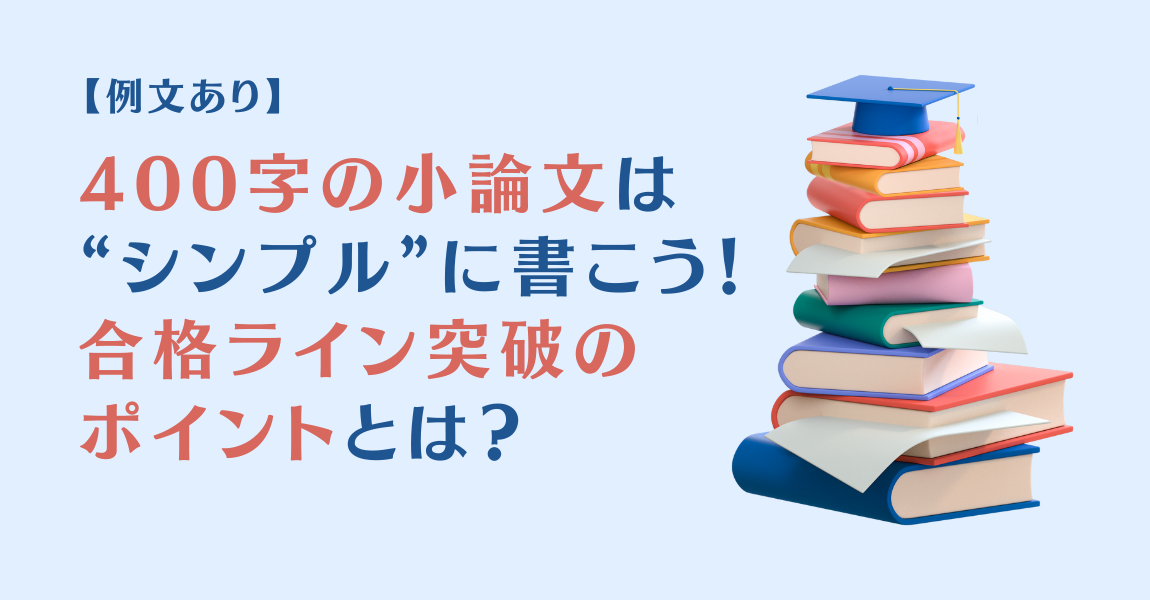
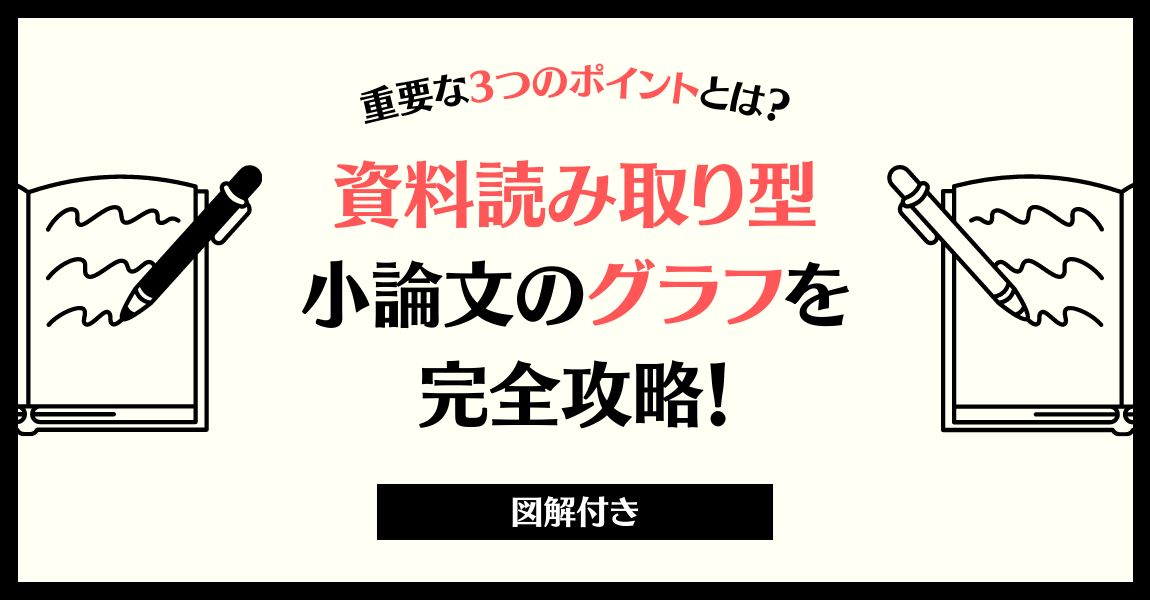
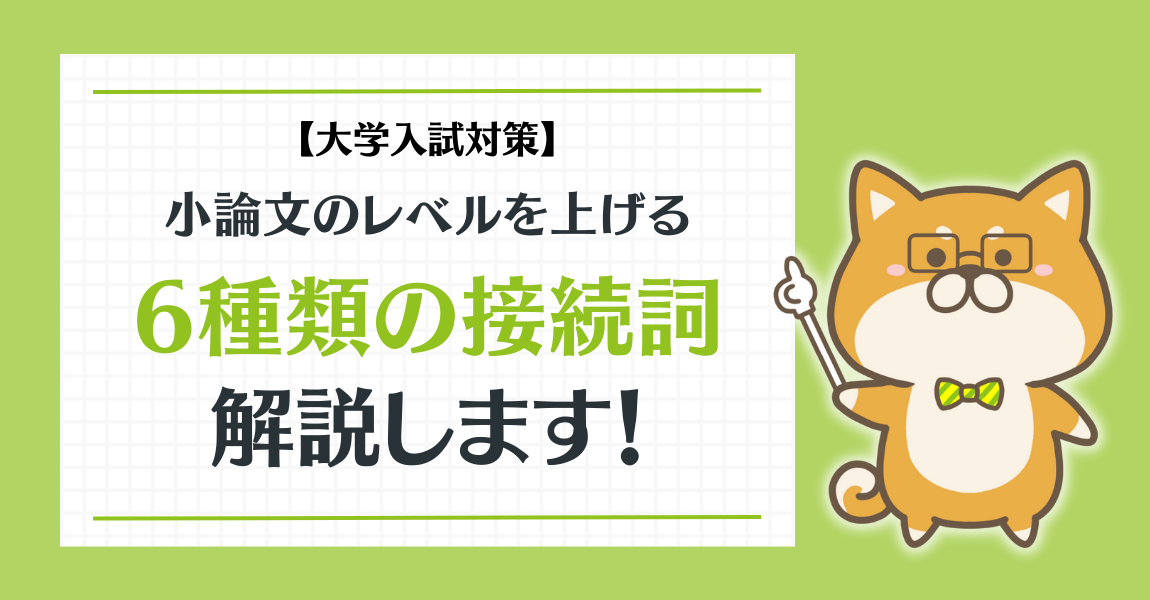
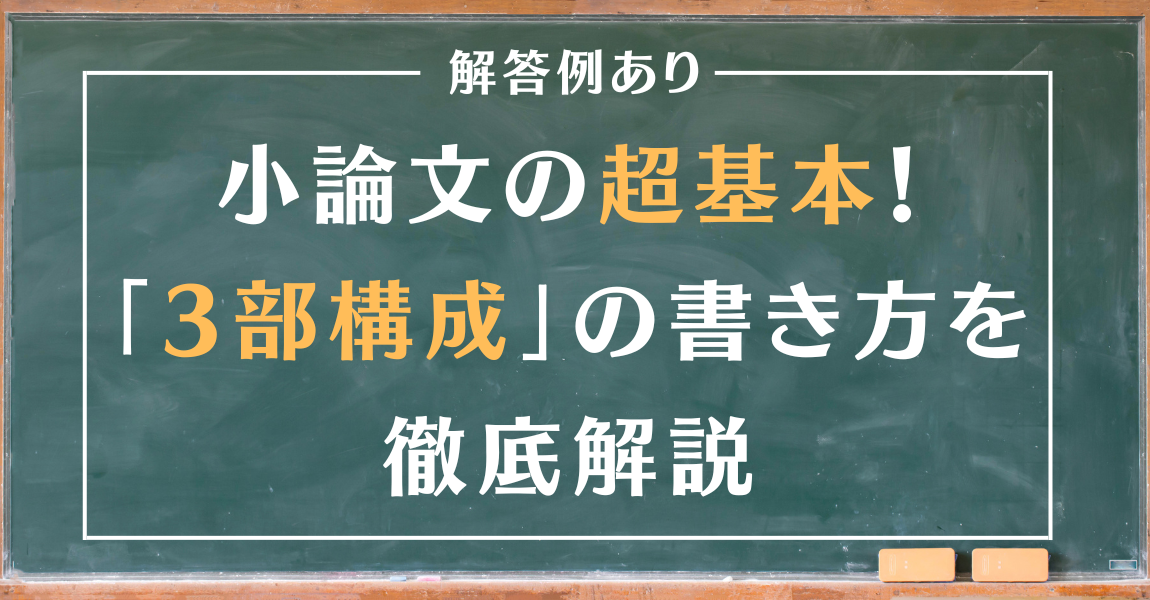

\役に立ったらシェアしてください!/