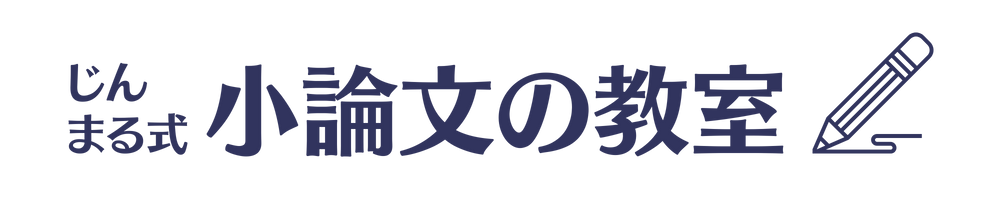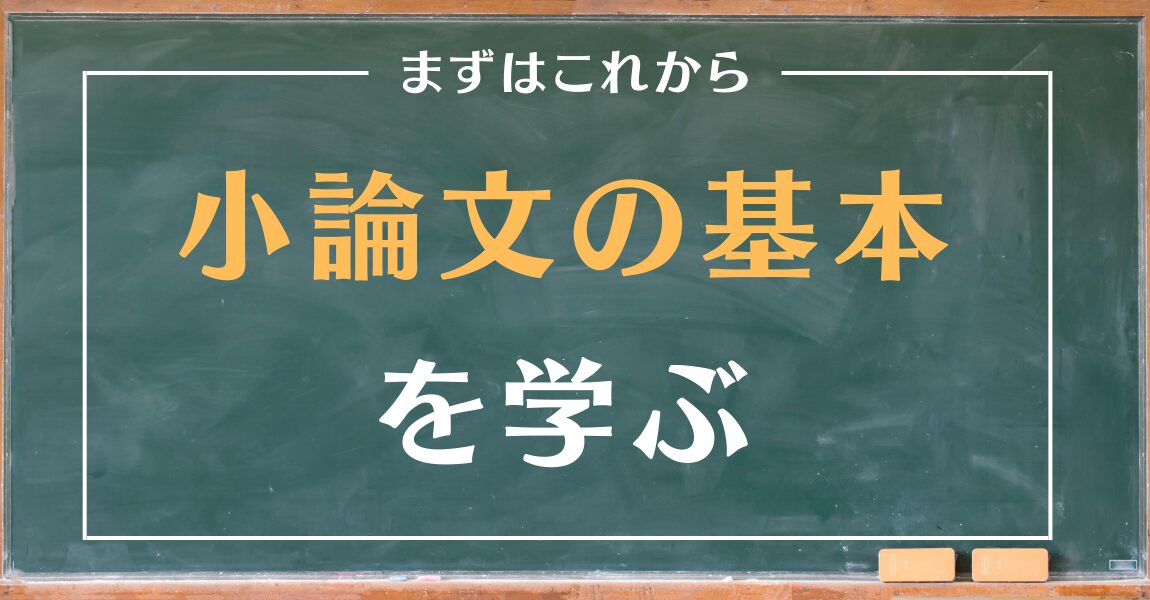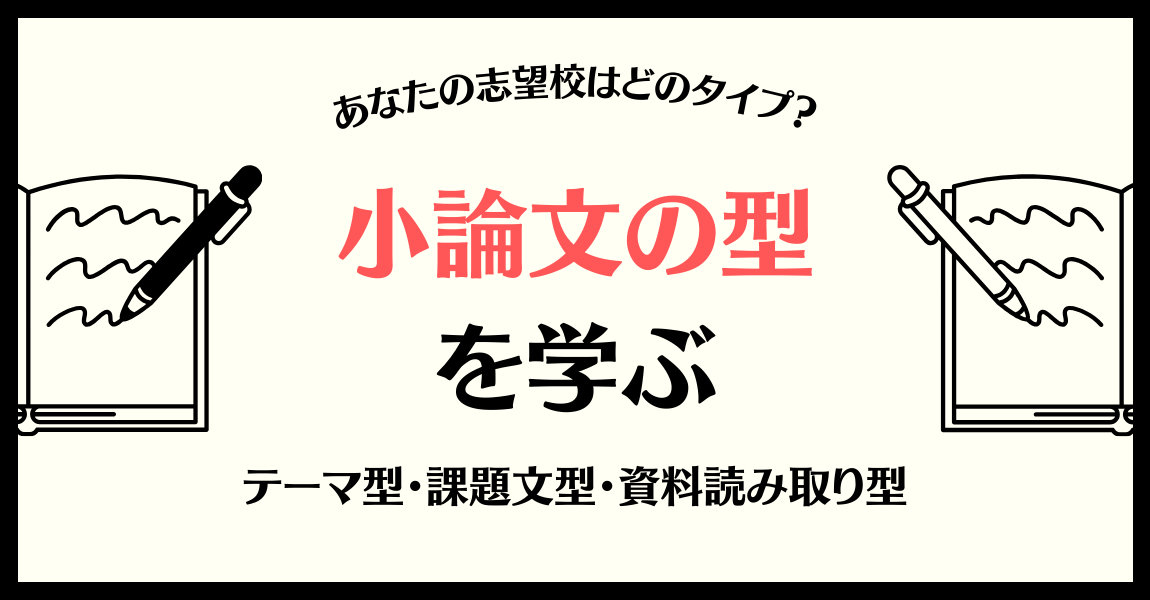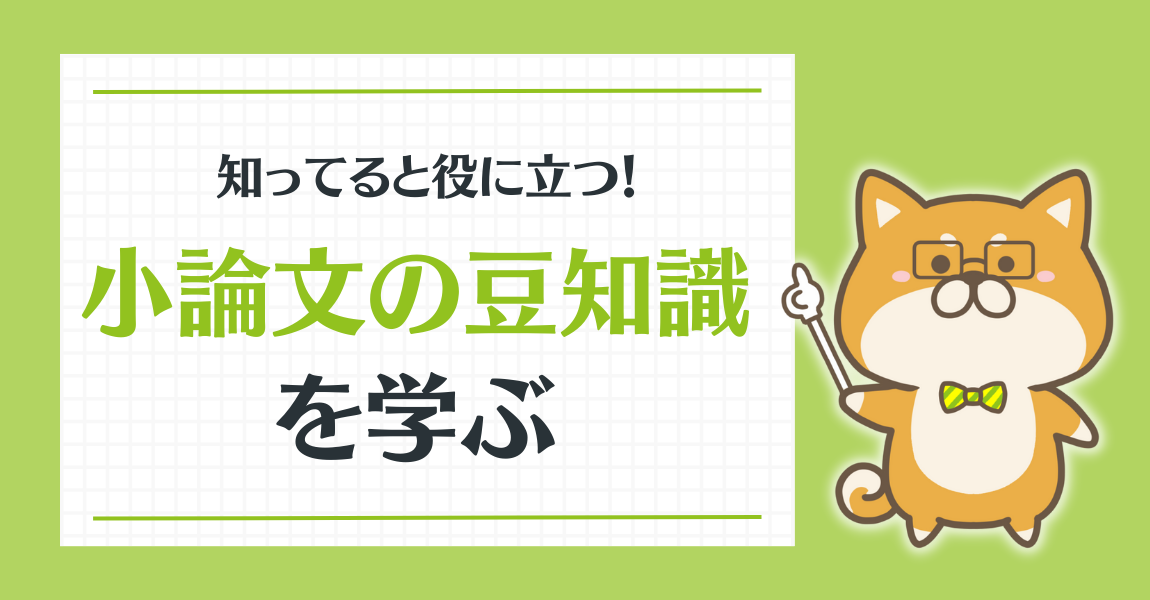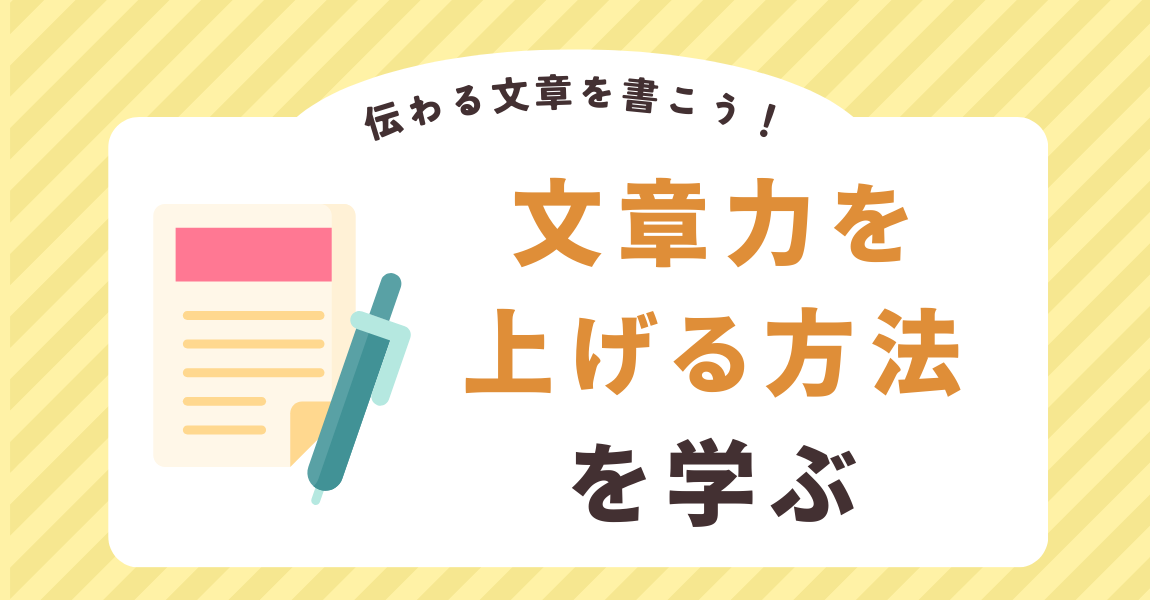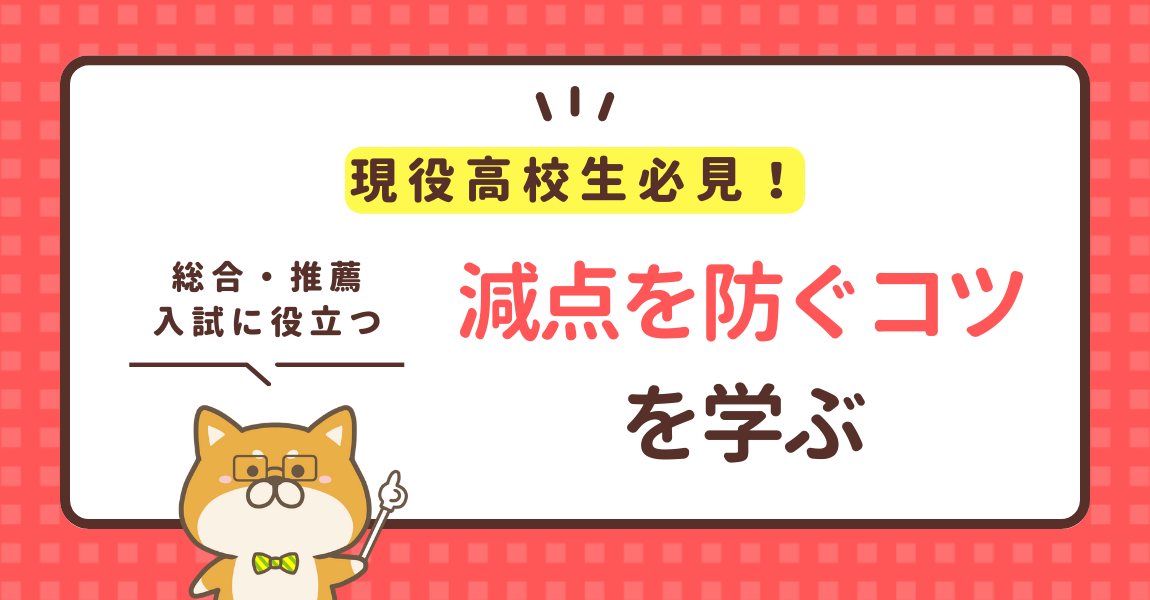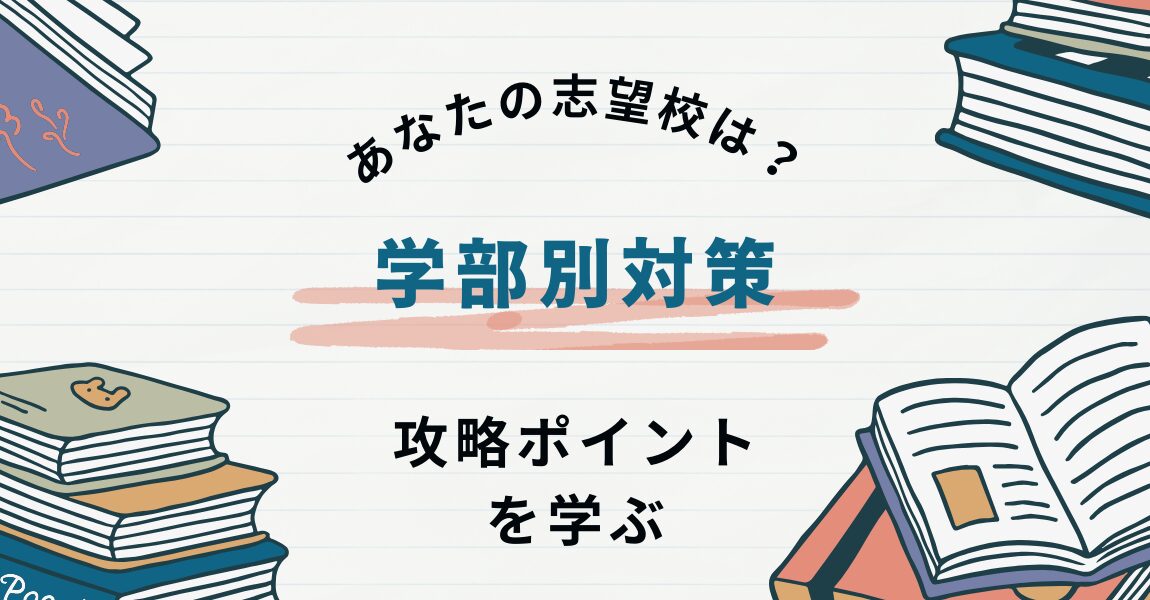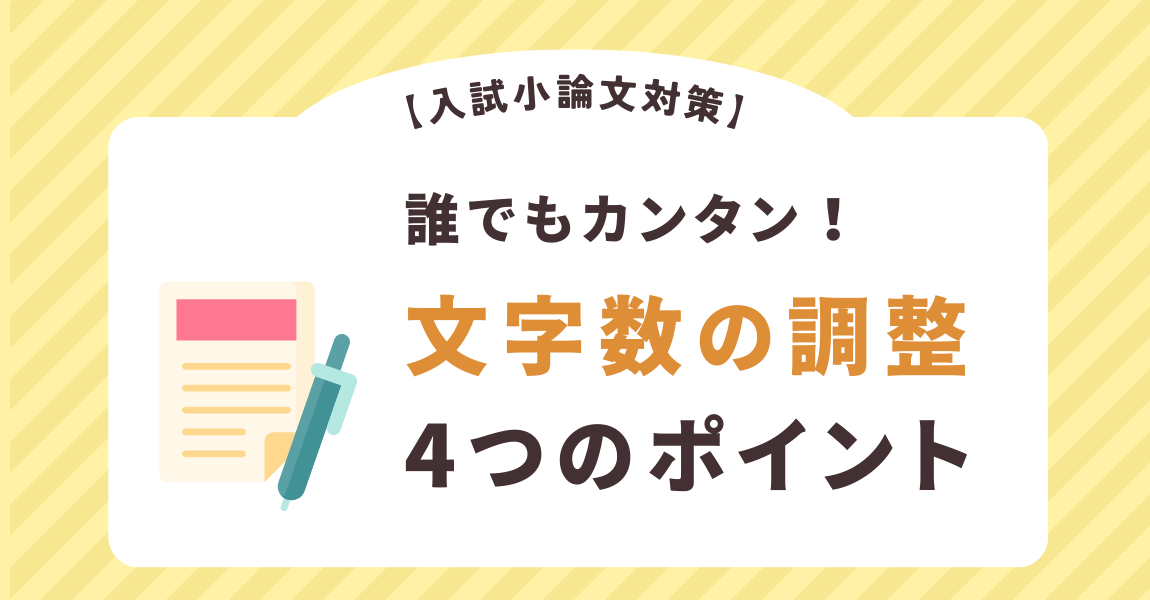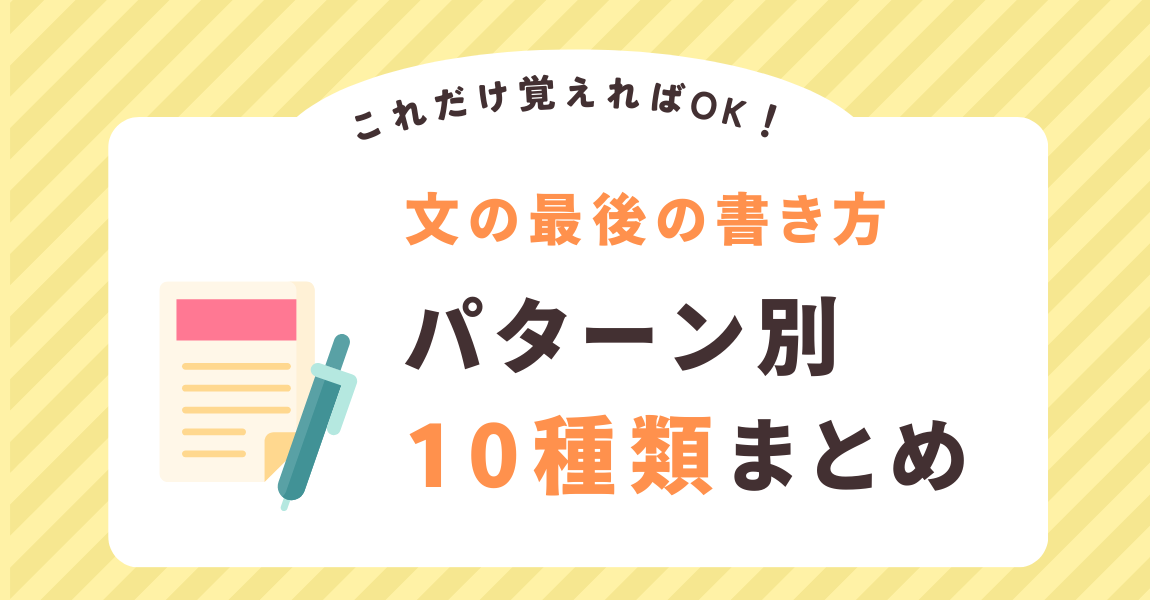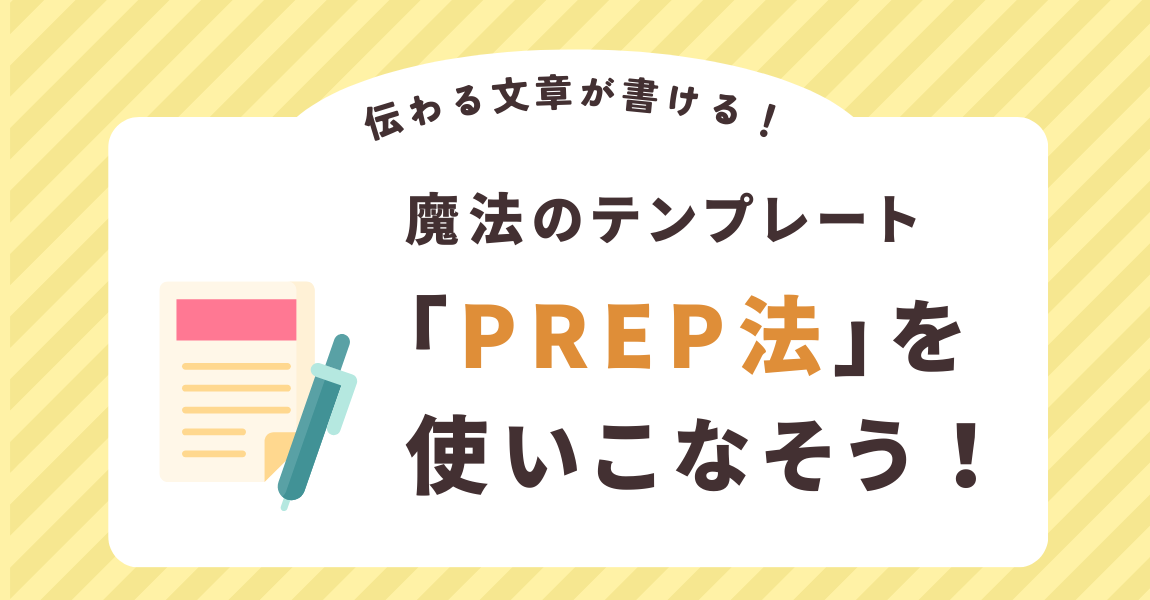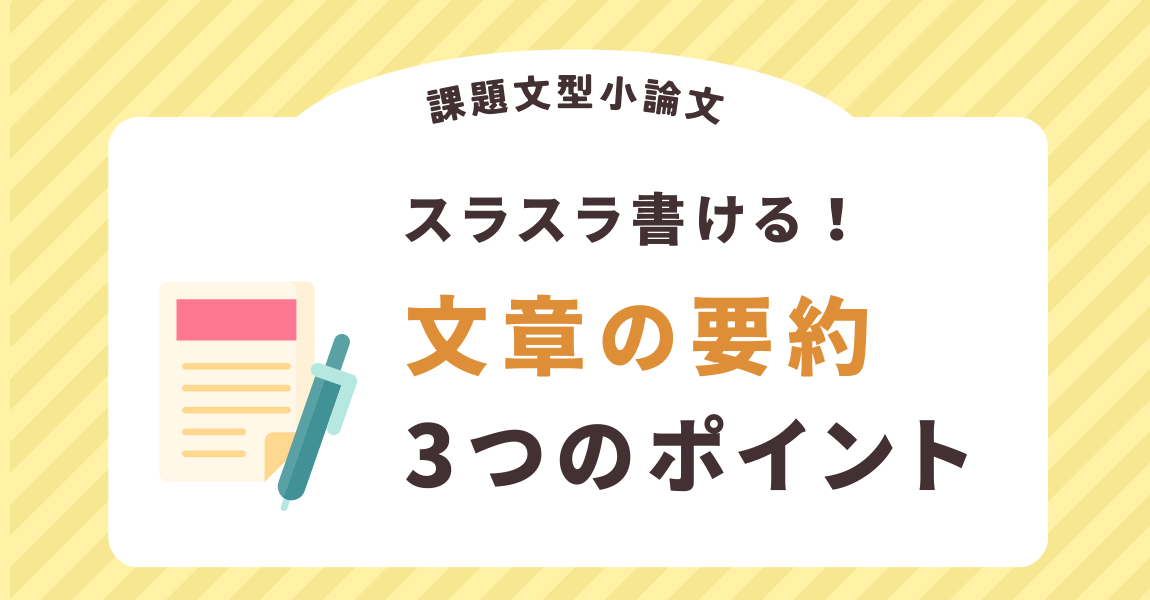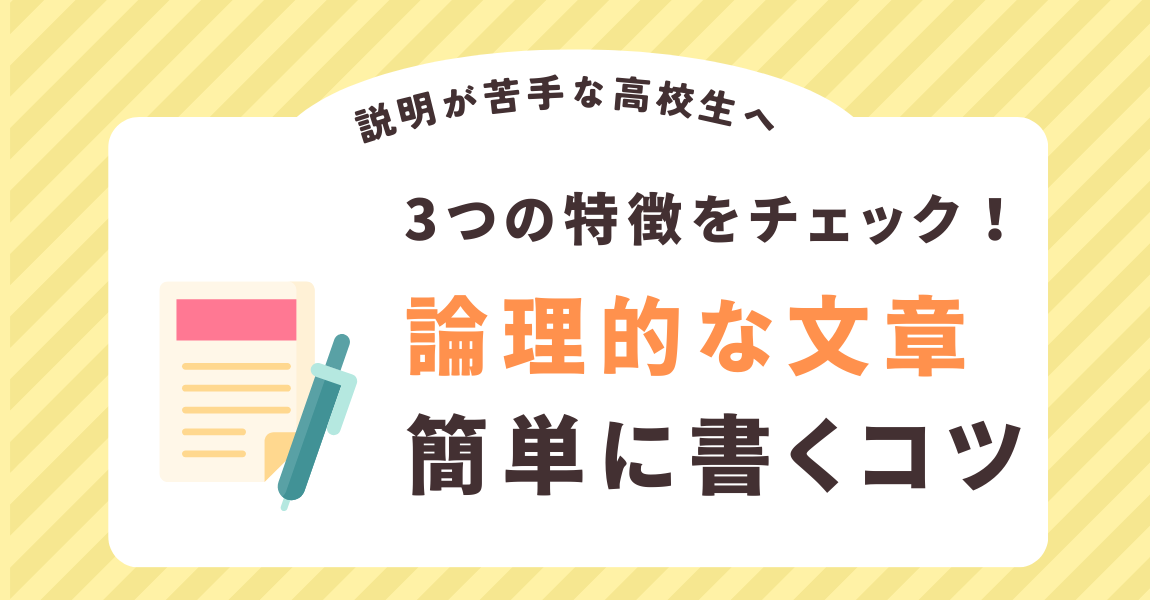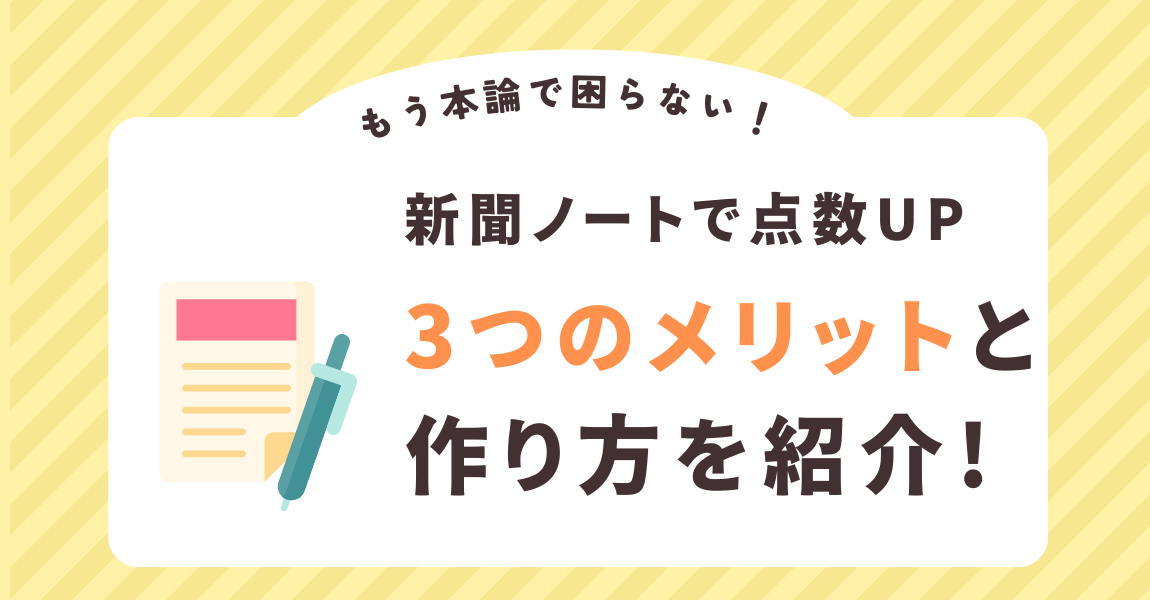スマホで完結!小論文に差がつく情報収集と整理のコツ(大学受験対策)
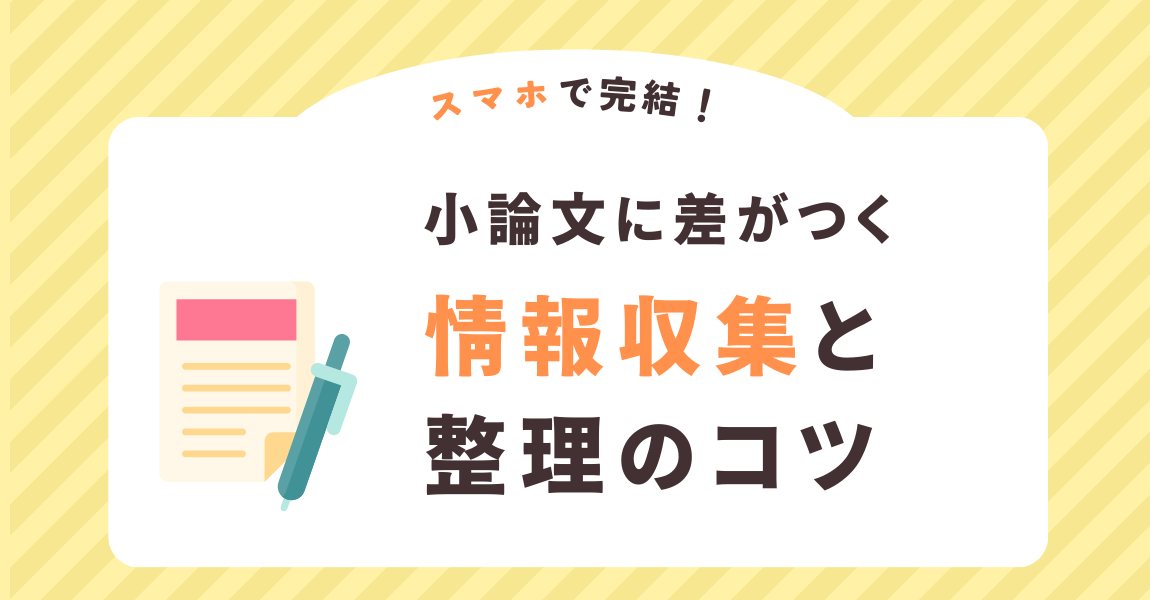
- 小論文で使えるネタがない
- いつも具体例が書けない
- 情報の集め方が分からない
この記事では、「スマホでできる小論文のネタ集め」についてなるべく分かりやすく説明します。
入試本番で「書くことがない、、、」とならないためにも、この記事で一緒に勉強していきましょう。
小論文でネタ切れを起こしていませんか?

小論文で使えるネタがなくて困っています。

使える情報を簡単に集められる方法はありますか?

この記事で「スマホでできる小論文のネタ集め」を実践すれば、材料に困ることがなくなりますよ。
小論文のネタ集めはスマホ1台でOK
小論文の練習をしているとき、「何を書けばいいんだろう」と悩んだことはありませんか?
書くべき内容が思い浮かばず頭を抱えてしまうのは、多くの受験生が経験することです。
そこでこの記事では、毎日持ち歩いているスマホだけで小論文のネタを集める方法を紹介します。
効率よく情報を集めて整理し、いつでも引き出せる「自分だけのネタ帳」を作りましょう。

ニュースアプリ、メモアプリ、写真機能の3つに絞ってポイントを解説します。
小論文のネタ集めに最適!3つのニュースアプリ
小論文に役立つ情報を集めるなら、ニュースアプリが便利です。毎日少しずつチェックして、気になる記事を読む習慣をつけましょう。

ここでは、特におすすめのアプリを3つ紹介します。
新聞やテレビ局の記事が自動的に集まるアプリです。同じニュースでも複数の視点から読めるので、多角的な理解が深まります。
「社会」「政治」「教育」などのカテゴリ別に整理されているため、小論文でよく出るテーマについて効率的に情報収集できます。時事問題対策にも役立ちますよ。
記事の下にコメント欄があるので、さまざまな立場の人の意見を読めます。賛成派と反対派の両方の視点に触れることで、自分の考えをより深められますよ。
また「あなたへのおすすめ」機能を活用すると、志望している学部や分野に関連するニュースを効率的に集められるので便利です。
ビジネスや社会問題に関するニュースを中心に扱っています。記事に専門家のコメントが付いているのが特徴で、複雑な経済問題や時事問題も分かりやすく解説されています。
経済学部や法学部を志望している人、社会問題について深く理解したい受験生におすすめです。
得点につながる「良いネタ」の見分け方
毎日ニュースを見ていると、たくさんの情報が目に入りますよね。しかし、そのすべてが小論文に役立つわけではありません。
「この受験生は考える力がある」と採点者に思わせるために、次のようなニュースを意識的にチェックしましょう。
一時的な話題ではなく、長く議論されているテーマ
「芸能人の結婚」のような一過性の話題より、「少子化問題」のような長期的な社会課題を選びましょう。時間をかけて議論されているテーマは、さまざまな視点から考察できるので、小論文対策に向いています。
賛否両論があり、議論できるもの
「台風による被害報告」のような事実報道より、「原子力発電の是非」のように意見が分かれるテーマに注目してみましょう。異なる立場の意見を比較し、自分の考えを示す練習になります。
自分の志望分野に関連するもの
志望学部に関連するテーマにも注目しましょう。医学部志望なら「医療制度改革」や「遠隔医療の普及」、教育学部志望なら「教育のICT化」や「不登校問題」など、どんなことが関係しそうかという視点で探してみてください。
社会的な意味があるもの
「新型スマホの発売」のような商品情報より、「デジタル依存の問題」や「情報格差」のような社会的課題を含むニュースを選びましょう。「なぜそれが重要なのか」を説明できるテーマが理想的です。
具体的な事例や数字が含まれるもの
抽象的な議論だけでなく、具体的なデータや事例があるニュースも探してみましょう。「〇〇県での実証実験の結果」や「〇〇%の増加」などの数字は、小論文に説得力を持たせる材料になります。
「小論文視点」でニュースを読むための3ステップ
いいニュースを見つけられても、なんとなく読んでいるだけでは高得点につながりません。
入試で高い評価を得るためには、情報を鵜呑みにせず、多角的に分析する習慣をつけることが大切です。

ここからは、ニュースの読み方を3つのステップに分けて解説します。
STEP1:事実と意見を区別する
ニュースには「客観的事実」と「記者や関係者の意見」が混在しています。まず5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)を整理して、事実部分を正確に把握しましょう。特に「なぜ」は問題の本質を理解するのに重要です。
STEP2:多角的視点で考える
次は、その問題についてどんな立場の人がいて、それぞれどんな主張をしているのか考えます。例えば「政府」「企業」「消費者」「専門家」など、さまざまな立場からの意見を整理してみましょう。小論文では一方的な意見だけでなく、反対意見にも言及できると説得力が増します。
STEP3:自分の意見と根拠を考える
最後に、「私はこう考える」と自分の立場を決め、その理由を具体的に考えてみましょう。「なぜそう思うのか」「どんな事例やデータがあるのか」「反対意見に対してはどう反論するか」まで考えられると理想的です。

以下のようにまとめておくと、あとで復習できるので便利ですよ。
STEP1:事実と意見を区別する
文部科学省が高校での携帯電話の校内持ち込みルールを緩和する方針を示した。理由は緊急時の連絡や教育利用の可能性を鑑みて。
STEP2:多角的視点で考える
【教育行政側】安全確保、教育ツールとしての活用、社会の変化への対応
【教員側】授業運営への影響、新たな指導負担の増加
【生徒側】利便性向上、自己管理能力の育成機会
【保護者側】連絡手段の確保、SNSトラブルへの懸念
STEP3:自分の意見と根拠を考える
携帯電話の持ち込み自体は現代社会の実情を考えると認めるべきだが、使用場面を限定したルール作りと情報モラル教育の強化が必要だ。特に、授業中は原則として使用禁止とし、教育目的で使う場合は教員の指示のもとで行うべきである。また、ルール導入前に生徒・教員・保護者を交えた議論の場を設け、学校ごとの実情に合わせたガイドラインを作成することが望ましい。
【志望学部別】専門性アピールのためのニュース活用法
志望学部に関連するニュースを日頃からチェックしておくと、小論文で専門分野への関心と理解をアピールできます。

ここでは、学部別の注目ジャンルを紹介します。
医療制度改革、感染症対策、医療技術の進歩、医師・看護師の働き方改革、地域医療、予防医学
教育改革、学習指導要領の改訂、不登校・いじめ問題、教育格差、ICT教育、教員の働き方
憲法改正議論、裁判員制度、少年法改正、国際法、プライバシー権、AI時代の法整備
経済政策、企業の社会的責任、SDGs経営、働き方改革、国際経済、デジタル経済
科学技術の発展、環境問題、エネルギー問題、AI・ロボット技術、宇宙開発、デジタル社会
食料安全保障、農業の持続可能性、遺伝子組み換え技術、食品ロス、気候変動と農業、地域活性化
外交問題、国際協力、多文化共生、難民問題、グローバル経済、国際機関の活動
志望学部に関連するニュースを読む際は、単に知識を増やすだけでなく、「その分野の専門家ならどう考えるか」という視点で考察する習慣をつけましょう。
メモアプリで作る小論文ネタ帳
ニュースをチェックしたら、そこから得た知識や考察を整理しておきましょう。実際に小論文を書くときの強力な武器になります。
スマホのメモアプリを活用して、あなただけのネタ帳を作りましょう。
おすすめのメモアプリ4選
メモアプリは、自分が使いやすいもので構いません。機能のちがいよりも、継続して使えるものを選ぶことが大切です。
最初は機能をシンプルに使い、慣れてきたら活用法を広げていくのもいいですね。

それでは、おすすめのメモアプリと特徴を紹介します!
Evernote
- 情報整理に強く、ウェブクリッピング機能が便利
- 多様な情報(テキスト、Web、PDF、画像、音声など)を一元管理できる
- ノートブックとタグで階層的に整理可能
- OCR機能で画像内の文字も検索できる
- 無料版は月60MBまでの容量制限あり、同期は2台まで
Microsoft OneNote
- 自由なレイアウトで情報を記録・整理できる
- テキスト、手書き、画像、PDFなどを好きな場所に配置可能
- 「ノートブック」→「セクション」→「ページ」の階層構造で整理
- Microsoft Office製品との連携が容易
- Microsoftアカウントがあれば無料で利用可能
Google Keep
- シンプルで使いやすく、タグ付け機能も充実
- 付箋のように手軽にメモが取れる
- テキスト、チェックリスト、画像、音声メモに対応
- ラベルと色分けで分類できる
- 階層構造はないため、大量の情報整理には不向き
Appleメモ
- iPhoneユーザーならすぐに使える
- テキスト、手書き、チェックリスト、表、写真に対応
- フォルダとタグで整理可能
- 書類のスキャン機能でPDF化も可能
- Apple製品間でiCloud経由でシームレスに同期
- 基本的にAppleデバイスでの利用に限定
ネタ帳を充実させるコツ
1. 定期的な情報更新
定期的に内容を見直し、古くなったデータや意見は更新していきましょう。特に統計データは最新のものがベストです。日付も書いておくと、後で更新しやすいですよ。
2. 関連テーマの紐づけ
「教育のデジタル化」「スマホ依存」「情報モラル教育」など関連するテーマとのつながりをメモしておきましょう。複数の視点から見た文章を書けるようになりますよ。
3. キーワードのタグ付け
「教育」「テクノロジー」「社会問題」など、キーワードごとにタグをつけておくと、後で検索するときに便利です。志望学部に関連するタグをつけておくのもおすすめです。
4. 情報の見直し
週に一度でいいので、集めた情報を見直す時間を作りましょう。そのときに「この問題についてさらに深く考えたいこと」をメモに追加すると、考えが深まります。
情報収集・整理のための最強テンプレート
ニュースを読んだら、以下の形式でメモに残しておくと、後で小論文を書くときにすぐに活用できます。ぜひ試してみてください。
【出典】
○○新聞 2023年5月15日(URLもあればなお良い)
【事実・データ】
・文科省が校内持ち込みルールを緩和する方針
・現在約5割の高校が校内持ち込み禁止
・海外では約7割の国が学校での使用制限あり
【賛否両論】
・賛成派:緊急連絡、教育ツール活用、社会変化への対応
・反対派:授業中の集中力低下、SNSトラブル、依存症リスク
【自分の意見】
持ち込み自体は認めるべきだが、使用場面を限定したルール作りと情報モラル教育の強化が必要。
【具体例・エピソード】
・自分の高校では朝に預ける方式だが、下校時の連絡に不便を感じる
・英語の授業で辞書として活用した経験が学習に役立った
【関連キーワード】
デジタルデバイド、情報リテラシー、学校自治、生徒の自己管理能力
写真機能を活用した情報収集術
スマートフォンのカメラ機能を活用すれば、テキストを入力する手間なく情報を残せます。
写真やスクリーンショットを上手に使って、小論文の説得力を高める材料を集めましょう。
学習資料を写真で効率的にストック
教科書や参考書の重要ページは、いつでも見返せるよう撮影しておきましょう。特に以下のような情報は、小論文を書くときの武器になります。
- 統計データやグラフ
- 重要な定義や概念の説明
- 事例や具体例の紹介
- 年表や歴史的経緯
デジタル時代の「切り抜き」術
インターネットやアプリで見つけた記事は、スクリーンショットで保存しておきましょう。

保存する際は、以下のポイントに注意してください。
- 記事全体が読めるように撮影する
- 日付・媒体名・著者名などの出典情報を必ず含める
- URLやQRコードも一緒に撮っておく
- 撮影後すぐにメモアプリに「なぜこの記事が重要か」の一言を添える
新聞や雑誌のなかで小論文に使えそうな記事を見つけたときも、写真に収めておきましょう。
それ以外にも、記事を切り抜いてノートにまとめておくのもオススメです。
小論文対策に役立つ新聞ノートの作り方を以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
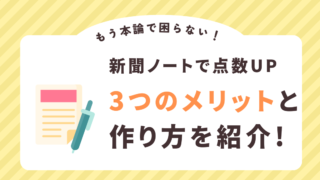
街中で見つける「リアルな社会課題」
日常生活の中にも、小論文に使える材料があふれています。以下のようなものを見つけたら、ぜひ写真に収めておきましょう。
- 広告、ポスター、標語:時代の価値観や課題が反映されている
- 博物館の展示物:専門的な情報や歴史的背景を学べる
- 公共施設の案内やパンフレット:行政の取り組みや社会サービスを知れる
- 街の風景や変化:都市開発、環境問題、人口動態などを視覚的に捉えられる
4つの習慣で引き出しを増やそう
小論文の質を決めるのは、試験前の対策だけではありません。日々の小さな習慣が、あなたの思考力と表現力を大きく成長させます。
スマホを活用して、無理なく続けられる習慣を身につけましょう。
① 1日5分のニュース要約
毎日1つのニュースを選び、スマホのメモアプリに日付とともに記録していきます。100字程度で要約する習慣をつけましょう。
要点をすばやく把握できる、文章表現力が向上する、時事問題への理解が深まるなど、小論文に欠かせない力が身に付きます。
② 反対意見を考える練習
気になったニュースや記事に対して、あえて自分とは反対の立場から見た意見を書いてみましょう。
小論文の中には、賛成反対を問われることも多いです。そのため、ただ自分の意見を述べるよりも、あえて真逆の意見を取り入れることで文章の説得力が増します。
偏った考え方を無くすためにも、このトレーニングは効果的ですよ。
③ 「なぜ?」を繰り返す
ニュースを読んだとき、「なぜそうなるのか」という問いを3回連続で自分に投げかけてみましょう。そうすることで、自分のなかでの理解が深まっていきます。
論理的に考える力も身に付くので、普段から「なぜ?」という視点を持てるといいですね。
④ スマートなSNS情報収集術
TwitterやInstagramを活用して、通学時間に情報をチェックする習慣をつけましょう。スキマ時間を利用すれば、効率よく小論文対策を進められます。
SNSを活用する際は、以下のようなアカウントがおすすめです。
- 新聞や報道機関の公式アカウント
- 志望分野の専門家や研究者
- 政府機関や国際機関の公式アカウント

情報の偏りに注意して、多様な立場の情報源を選びましょう。
これらの習慣は、それぞれが5分程度で実践できるものばかりです。すべてを一度に始めるのではなく、まずは一つだけ選んで1週間続けてみましょう。
習慣化されたら次の習慣を加えていくことで、無理なく小論文力を高められますよ。
スマホでできる小論文のネタ集めまとめ
「スマホでできる小論文のネタ集め」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
スマホという身近なツールを活用すれば、いつでもどこでも小論文対策ができます。
今日から少しずつ、自分だけの「小論文ネタ集」を作り上げていきましょう。
- ニュースアプリを活用する
- 調べた内容はメモアプリにまとめる
- 写真機能を活用する
小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。
この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。
何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!
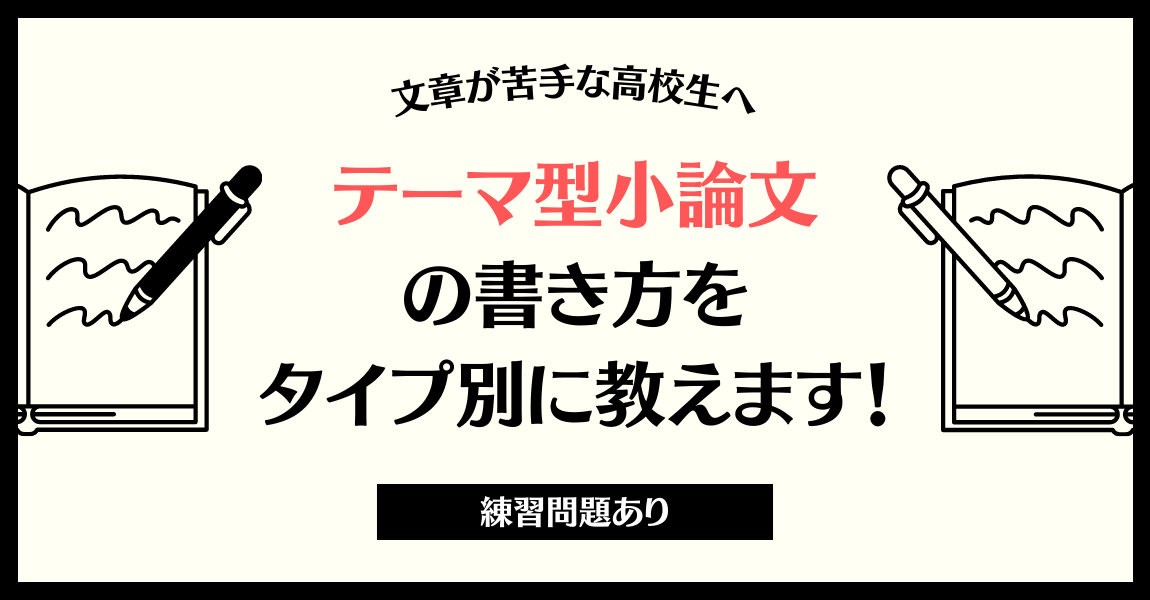
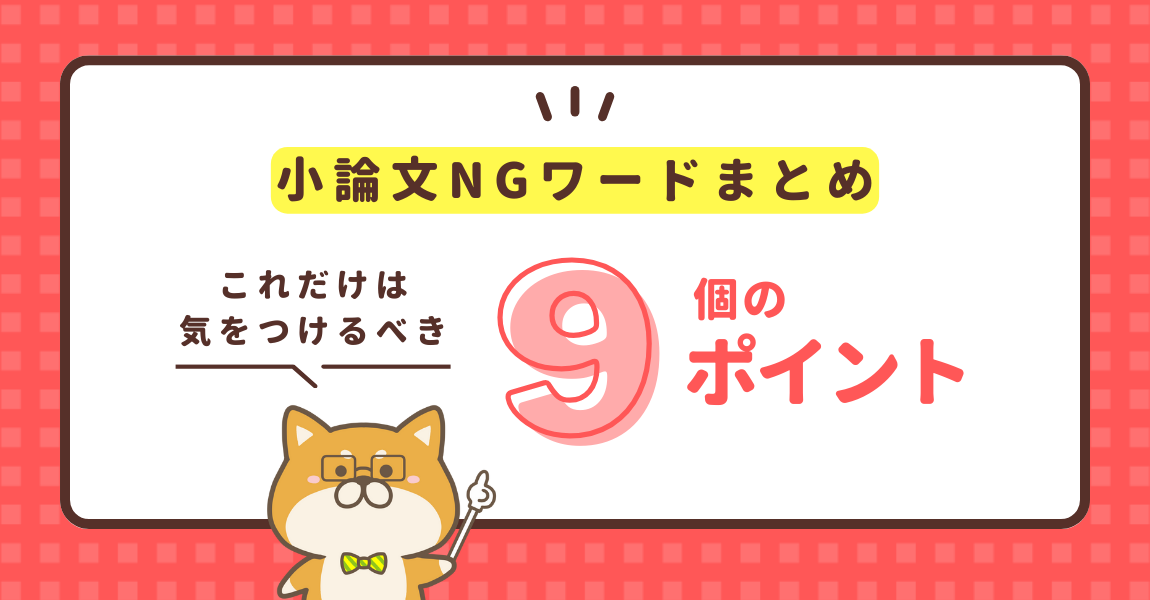
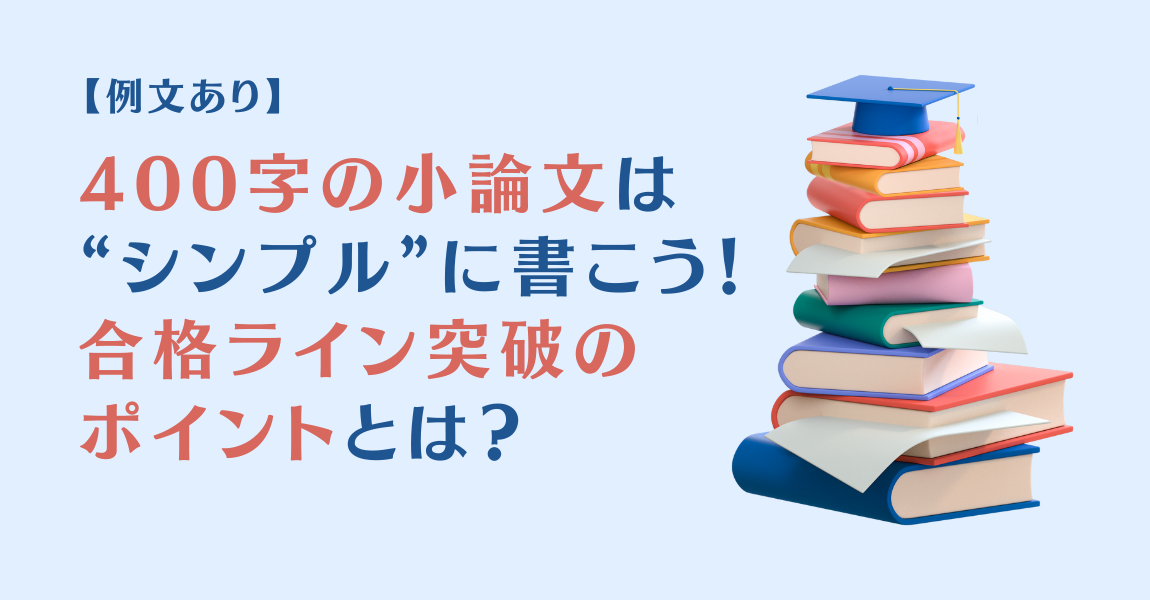
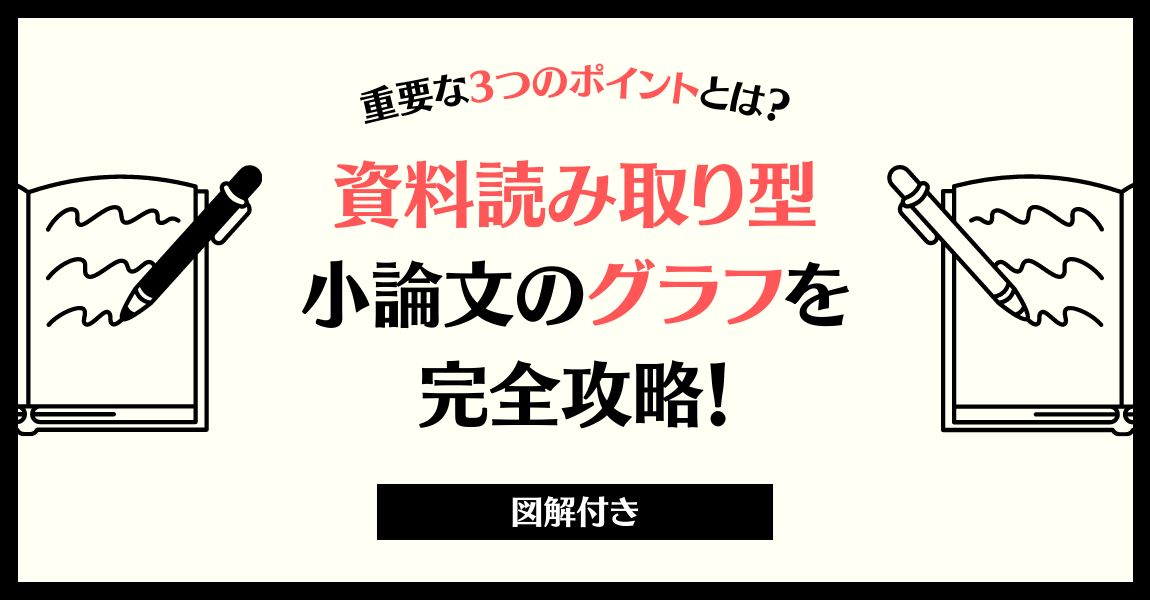
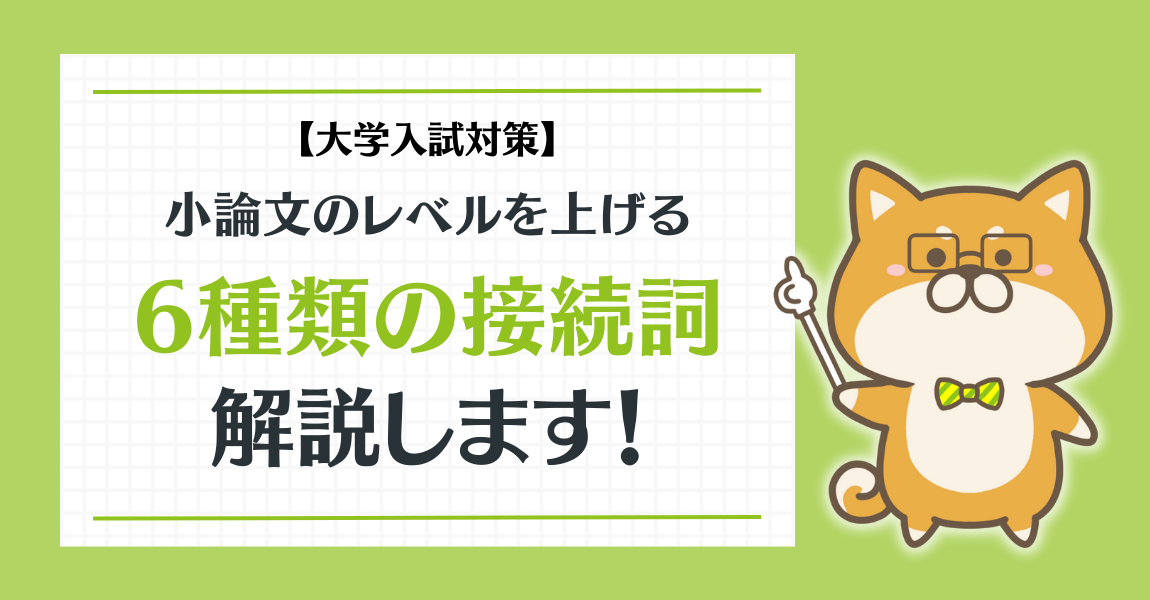
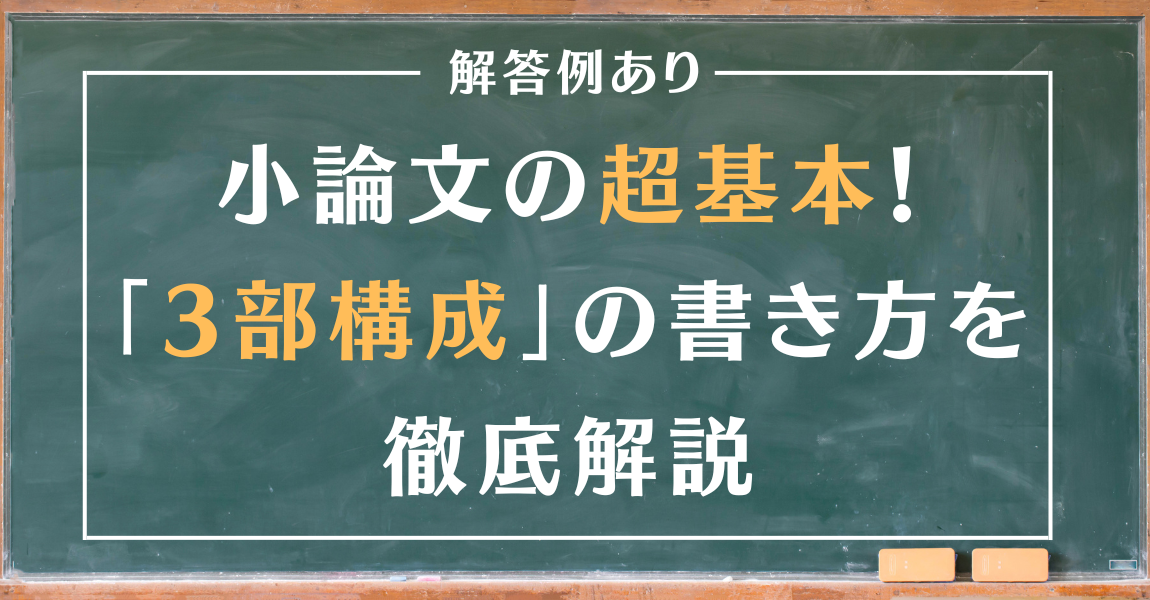

\役に立ったらシェアしてください!/