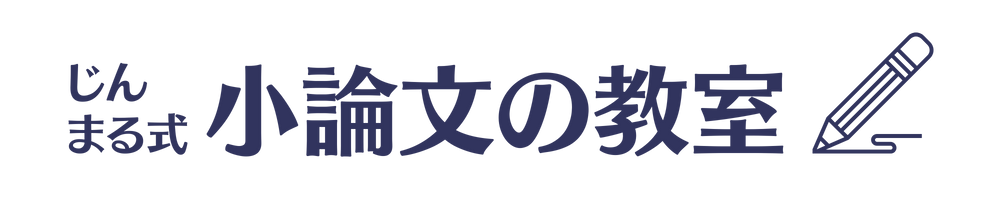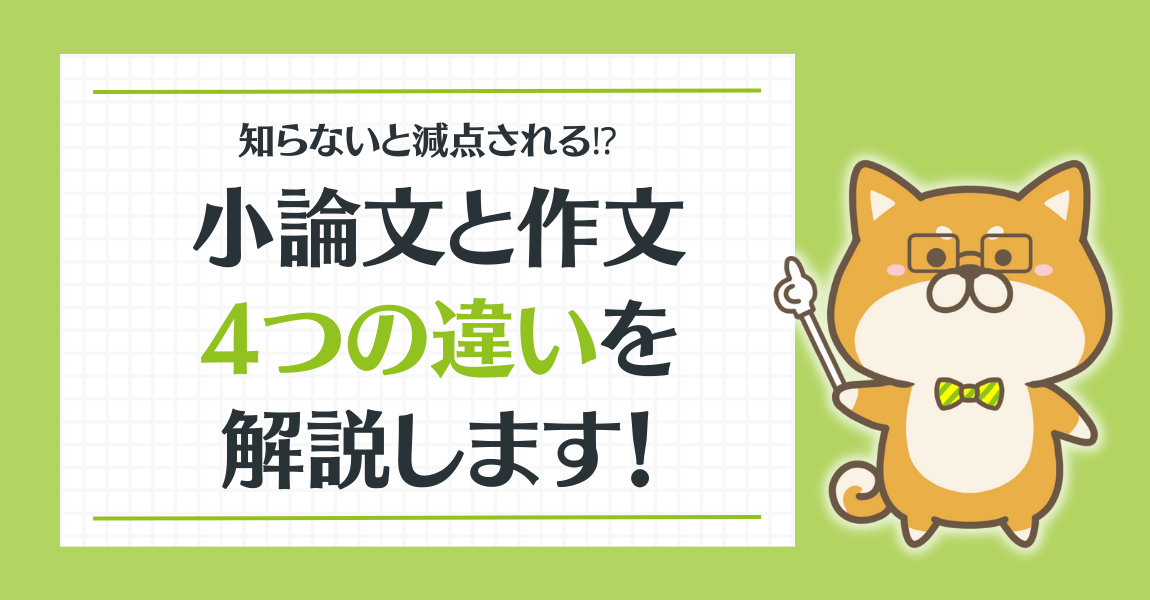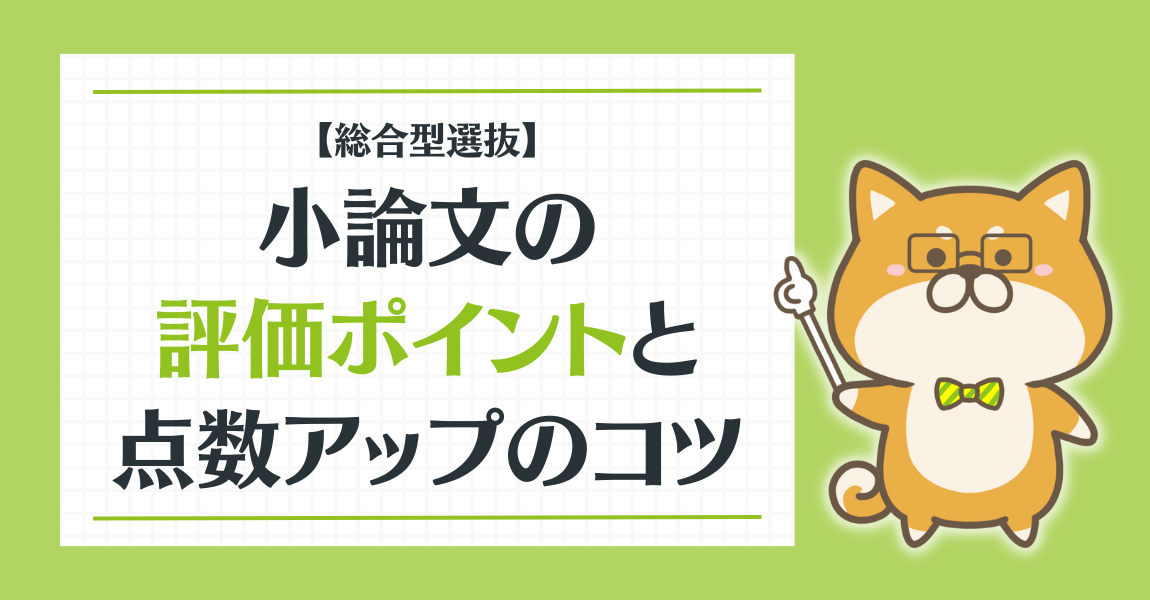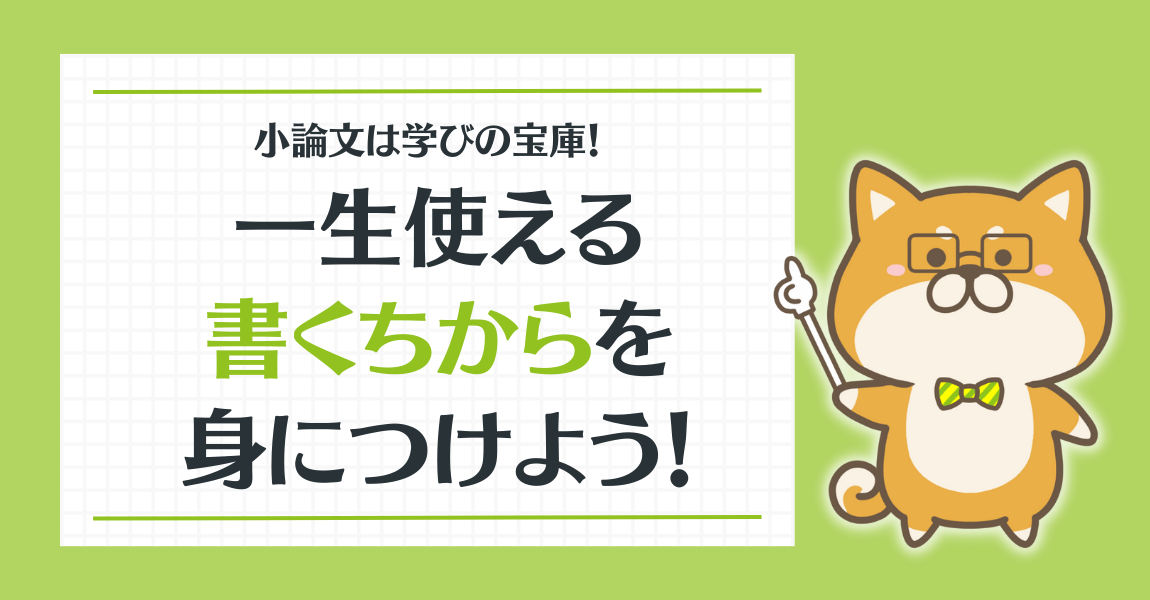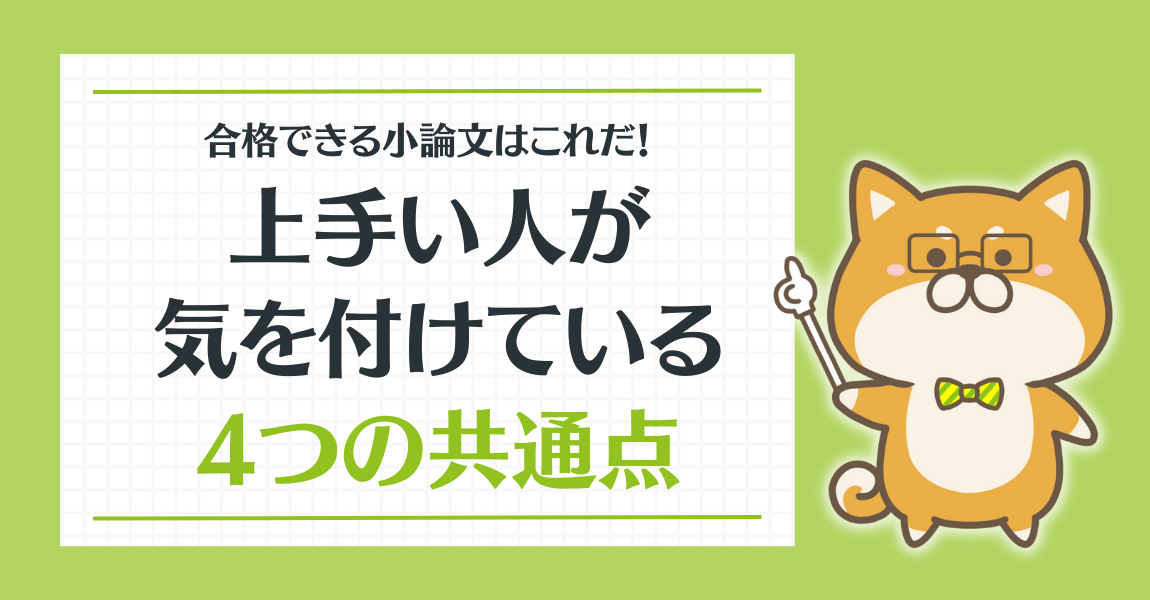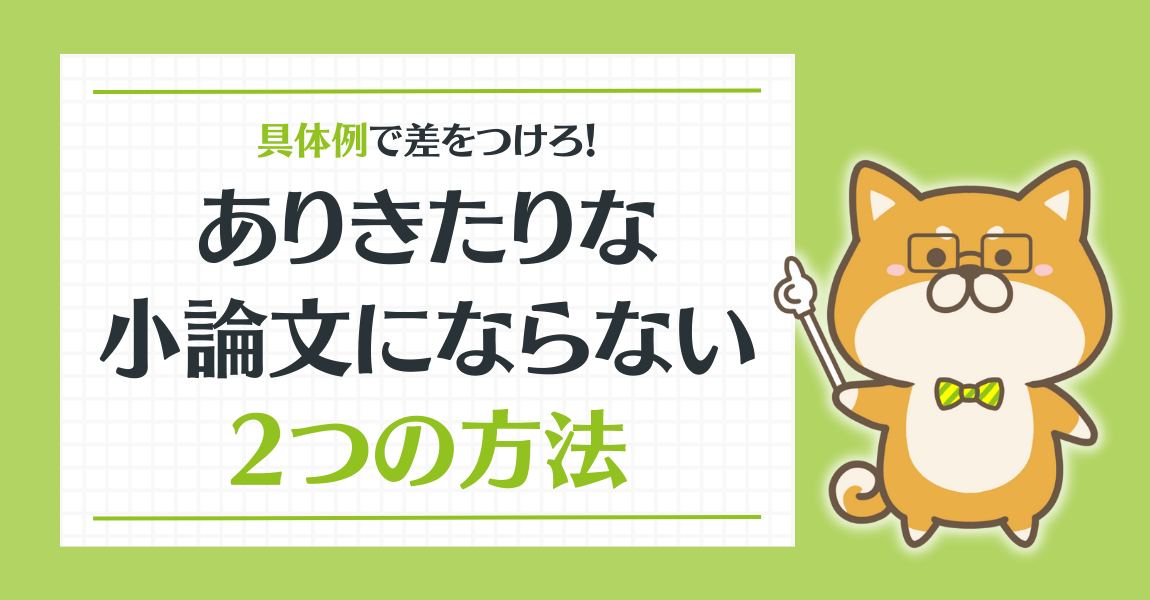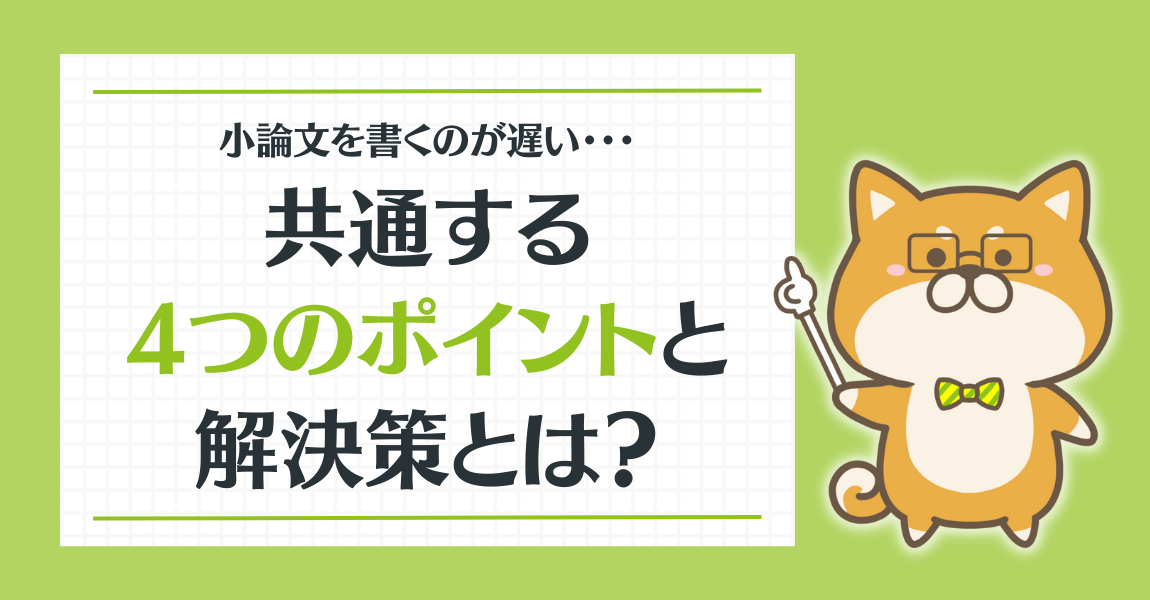【初公開】小論文がみるみる上達!5つの勉強法を紹介します(高校生向け)
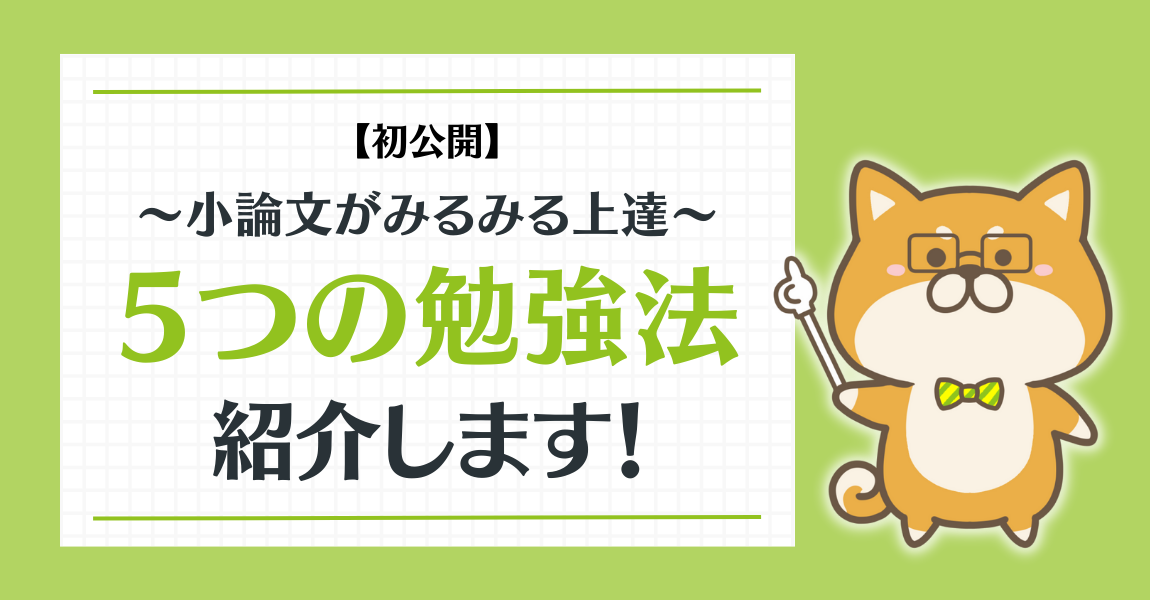
- 小論文の勉強法が分からない
- ただ過去問を解くだけで終わっている
- なかなか書けるようにならない
この記事では、「小論文の勉強法」についてなるべく分かりやすく説明します。
小論文対策の効率を上げるためにも、この記事で一緒に勉強していきましょう。
ただ何度も書くだけでは上達しない

過去問を解く以外の勉強方法が分かりません。

このやり方で志望校に合格できるか不安です。

この記事で紹介する「小論文の勉強法」を実践すれば、勉強の効率が一気に上がりますよ。
勉強時間をムダにしていませんか?

ショウくん、ロンさん、いつもどんな風に小論文の勉強をしていますか?

参考書を読んだり、例題や過去問を解いたりしています。

国語の先生に、たまに添削してもらっています。
今この記事をご覧のあなたは、どのように小論文対策を進めていますか?
ショウくんやロンさんと同じように、参考書の例題や過去問を解いて、先生に添削してもらうという流れで進めている人が多いのではないでしょうか。
もちろん、文章を書くのが得意だったり、小論文の書き方が身に付いているという人はそれでもかまいません。
小論文対策をするうえで、何度も書くということはとても大事なことですからね。
しかし、なかなか上手に書けないという高校生がこのような勉強法をしてしまうと、非常に効率が悪いんです。
せっかく勉強しているのに、なかなか結果が出ないのはもどかしいですよね。
そうならないためにも、効率的な勉強法を身に付けてあなたの小論文をレベルアップさせましょう。
小論文が上達する5つの勉強法
本題に入る前に、ひとつだけお伝えさせていただきます。
今から紹介する方法は、小論文の基本をある程度理解できているという人向けのものです。
これから小論文対策を始めるという高校生は、まず小論文の基本から学ぶことをおすすめします。
小論文の基本については以下の記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
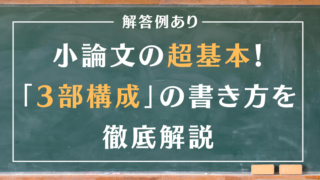

小論文対策が思うように進んでいないという人は、これから紹介する方法を実践すると、勉強の効率が一気に上がりますよ。
①模範解答を丸写しする
「いざ問題を解こうとしても、なかなか書けなかった」
今この記事をご覧のあなたも、こんな経験があるのではないでしょうか。
そんなときにおすすめなのが、模範解答を原稿用紙に丸写しすることです。

丸写しをして意味があるんですか?

模範解答を書き写すことで、こんなメリットがありますよ。
- 小論文の構成を学べる
- 原稿用紙の使い方が身に付く
- 文字を書くスピードが分かる
- 言葉のレパートリーが増える
- 事例を他で転用できる
このように、模範解答の丸写しは良いことだらけなのです。
では早速、以下の解答を丸写ししてみましょう。
原稿用紙が手元にない人は、ノートでも裏紙でも構いません。
まずは一度書き写してみることが重要です。
私は、成人年齢が18歳へ引き下げられたことに賛成だ。なぜなら、若者の積極的な社会参加を促すきっかけになるからである。
たしかに、日本の場合は18歳の多くがまだ高校生だ。そのため、社会経験が不足している、経済的に自立していないなど、成人と呼ぶにはまだ早いという意見もあるだろう。しかし、成人を迎え自由と責任を負う立場になるからこそ、自覚が芽生えるのではないだろうか。そして、法務省が説明しているように、若者の自己決定権を尊重することは、積極的な社会参加を促すことに繋がると考えられる。また、世界的に見ても成人年齢を18歳と定めることが主流となっている。それに加えて、少子高齢化が進行している日本だからこそ、若者の社会参加の機会を早めることには大きな意味があると言える。
以上のことから、私は成人年齢が18歳へ引き下げられたことに賛成する。
②メモの作り方を練習する
次は、小論文の設計図となるメモの作り方です。
小論文が思うように書けない高校生の多くは、メモを上手に作れていません。
以下の内容で思い当たることがある人は、メモの練習に時間を使いましょう。
- 書いてる途中で分からなくなる
- 話しが行ったり来たりする
- 序論から結論まで一貫していない

メモの練習をすると、短時間で効率よく小論文を書けるようになりますよ。
メモの作り方は以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
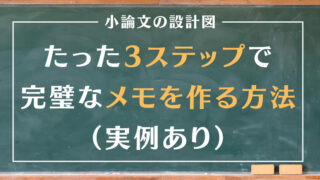
③文字数は徐々に増やす
過去問や練習問題に取り組む際、問題をそのまま解いていませんか?
結論から言うと、はじめから800字や1000字の小論文を書こうとしないでください。
なぜなら、最後まで書き終わらずに挫折してしまったり、自信を無くしてしまう高校生が多いからです。
まずは400字くらいから始めて、600字、800字、1000字と文字数を増やしていきましょう。

文字数を変えながら同じ問題を解いてみるのも、良い練習になりますよ。
④関連書籍を読む
ここまで書き方の練習方法をお伝えしてきましたが、それだけでは書けない場合もあります。
なぜなら、専門知識が必要な問題もたくさんあるからです。
小論文の問題は、志望校や学部学科によって出題テーマが異なります。
そのため、関連テーマについての知識が不足していると、何を書いたら良いか分からないという状況に陥ってしまうのです。
キーワードを調べる、関連する本やニュースをチェックする、新聞記事に目を通すなど、日ごろから情報収集のアンテナを立てておきましょう。

本や新聞を読む時間がないという人には、音声メディアがおすすめです!
⑤いろいろな人に添削してもらう
最後にお伝えするのは、なるべく多くの人に添削してもらうということです。
書く人によって文章のクセがあるように、添削する側も人によって注目する点が違います。
試験当日に書いた小論文も、どんな人が採点するか分かりません。
ですから、なるべく多くの人に添削してもらい、書き方のクセを直していきましょう。

友達同士でお互いに採点しあうことも効果的ですよ。
小論文の勉強法まとめ
「小論文の勉強法」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。
小論文は、ただ書いているだけでは上達しません。
今回紹介した勉強法の中から、自分に足りないものを積極的に取り入れてみてください。
①模範解答を丸写しする
②メモの作り方を練習する
③文字数は徐々に増やす
④関連書籍を読む
⑤いろいろな人に添削してもらう
小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。
この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。
何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!